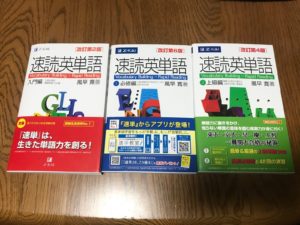当たり前のように行われてきた(と筆者のような者は思っている)小中学校の家庭訪問が岐路にあるという話です
おはようございます。
2019年4月のビルメン王提供の雑感ブログ配信記事です。
新学期が始まり、全国の小中学校では、PTA委員決めだの家庭訪問だの、その前の家庭調査票という名の謎の書類を「紙」で提出するなどの有職故実が、明治以来150年間に渡って行われている今日この頃ですが、みなさんいかがお過ごしでしょうか。
こんな状況だから、少子化が止まらないのだと思っています。
学校が出す連絡事項など、紙で児童や生徒に「配布」するより、電子掲示板にして、児童も生徒も保護者も学校関係者も、それを一覧できるようにした方が早いですし、宿題や授業すら、オンラインで代替できるところが相当あるところどうして行わないのか、本当に不思議に思っています。
そんな中、小中学校でずっと行われていた「家庭訪問」がついに任意制になったり、一斉にとりやめるという小中学校が出てきたことが話題となっています。
授業時間の確保や教師側の働き方改革で、全児童全生徒を対象にした家庭訪問はとりやめたり、希望制にするという対応をとる小中学校が出てきたというのです。
確かに、小中学校の教諭が児童生徒の自宅に出向いて保護者らを交えて懇談するという「家庭訪問」ですが、その意味は、もともと、①担任教諭と保護者らの顔合わせ、②児童生徒の自宅・通学路の確認、そして③児童生徒の家庭の状況を把握するといった目的で行われてきました。
このうち、①顔合わせについては別段自宅で行う必要はなく、学校の授業参観や土曜授業での公開授業の場を利用すれば十分ですし、②自宅の場所や通学路の確認も、住所がわかっているのであればインターネットの地図(要するにGoogleマップ)を利用してプロットして、教諭側で好きな時間に散策するなど確認すれば十分であります。
そして、③家庭の状況を把握するということですが、家庭と学校での教育の連携という美名はありましょうが、そんなのは「大きなお世話」であろうというのが現在のプライバシー権が確立した時代における大宗の意見ではないかと思われます。
ということで、組織業務改革の基本である、①なくせないか、②減らせないか、③まとめられないか、という業務のどれもに当てはまる項目になってきつつあるこの家庭訪問という「行事」については、上層部の決断次第で①もしくは③授業参観との統合ということで解決されるべき事柄だと考えています。
「緊急時には保護者の携帯電話に連絡して迎えに来てもらうのが一般的」
になってきているこの現代社会(平成年間の終わり)において、一律の家庭訪問を実施する労力が残っているのであれば、もっと違った授業形式を取るなどの対策が必要でしょう。
特に、小6生や中3生といった、「進路」を控えている児童生徒に対して、その保護者と担任がとっくり話し合う学校での三者面談という場をきっちり設ける方が、教諭側児童生徒側にとって、よほど有用であろうかと考えています。
AI人材の育成とか旗振りをする前に、そもそも簡単なIT技術を使った学校運営や教育システムの合理化が図られないか、そこにより注目していきたいと思っております筆者からのコメントは以上です。
(2019年4月22日 月曜日)
▷▷次のページは