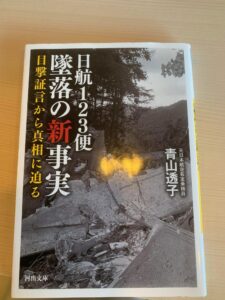Facebookアカウント復活

何故かいきなり復活
今日は2025/12/11である。実は一年半ものあいだ、Facebook のアカウントにログインできなかった。あの青い画面の向こう側に、自分のデータが確かに存在するはずなのに、ログインページは頑なに扉を閉ざし続けていた。まるで、こちらの声など聞こえもしないかのように。
最初の頃は「まあよくある不具合だろう」と軽く受け流していた。翌日になればログインできるかもしれない。数時間後には復旧しているのではないか。そんな淡い期待を胸に、適当なリトライを繰り返していた。
だが数日が過ぎ、数週間が過ぎ、ついには「一年半」という、もう笑うしかないような期間が経過してしまうと、状況は一変した。ログインの試行は、もはや実用的な行為ではなく、どこか宗教的な儀式めいてきた。暗号のように打ち込むメールアドレスとパスワード。回転する読み込み表示。無情に跳ね返されるログイン画面。そこに漂うのは「慣れ」と「諦念」である。
この一年半という期間は妙に長かった。日数に直すと約550日前後。数字で見ると、妙な重みがある。季節は春から夏へ、夏から秋へ、そして冬へ。人間の生活のほうは変化し続けるのに、Facebook のログイン画面だけは変わらない。こちらは1.5年も歳を重ねているのに、あちらは「ログインできませんでした」の一点張りで、ひたすら不親切な不動の石像のようだった。おかげさまで、予備試験短答に落ちるという経験まで味わった。
ところがである。つい先日、その石像が急に動き出した。こちらの操作も、特別変わったわけではない。同じ端末で、同じブラウザから、同じようにアプリ操作を試みただけだ。ところが突然、あの扉が「どうぞ」とばかりに開いたのである。予告もなく、説明もなく、ドラマの伏線回収もない。ひょい、と開く。拍子抜けとは、まさにこのことだ。
何かアプリがぐるぐる遷移し、画面が切り替わり、見慣れたアイコンや過去の投稿が並び始めた瞬間、思わず身をのけぞった。「嘘だろ」と口から漏れた。いつもなら「ログインに失敗しました」などと冷たく突き返すくせに、今日に限っては何事もなかったかのように、やあ久しぶり、みたいに歓迎してくる。広告もバッチリだ。
こちらとしては感動すべきなのか、怒るべきなのか迷う場面である。一年半ものあいだ閉め出しておいて、何事もない顔で「おかえり」と言われても困る。こちらは別に家出したわけでもなければ、勝手に遠ざかったわけでもない。向こうが鍵をかけていたのだ。それにもかかわらず、平然と「久しぶり」と言ってくるような態度である。ツンデレが過ぎる。確かに勝手に音信不通になった女が突然連絡してくることはある。しかしそういうのこそ気をつけねばならぬ。デキ婚リスクまっしぐらだ。
さて、ログイン後の画面には、あの空白の一年半に相当する通知が山のように積まれていた。もちろん、それらを細かく確認する必要はない。重要なものなど、最初から存在していなかった。ただ、冷静に通知を見つめていると「この一年半、向こうは向こうで自動的に時を重ねていたのだな」と妙な実感が湧いた。ログインできない間にも、データの世界は静かに動き続けていたわけで、そこに取り残されていた自分だけが妙に滑稽だった。浦島太郎である。
この「突然ログインできた」という出来事は、単にサービスの不具合が解消された、という一点に集約される。だが、こちらが受ける印象はそれだけでは済まない。一年半という空白期間の長さが、結果に対して妙な重量感を生んでしまうのだ。「なんで今日なのか」と考えてみても当然ながら答えはない。Facebook 側が「そろそろ許してやるか」と思ったわけではない。単なる偶然、たまたまの復旧にすぎない。にもかかわらず、こちらの側には妙なドラマ性が発生してしまう。
しかも、あまりにも突然だったものだから、ログインできた瞬間、一種の幻覚のような気さえした。あれだけ拒んでいた扉が開いたのだから、「もしかしてこれは夢で、ログインできていると思い込んでいるだけではないか」という疑念が頭をよぎった。何度も画面を更新し、アカウント情報が本当に表示されているか確認してようやく「これは現実だ」と理解できた。
この一年半の間に、こちらはログインを諦めて別のサービスを使い始めたりもした。Facebook は生活の中心にはなかった。だから、本来なら再ログインできても大した意味はないはずなのだ。ところが、長く閉ざされていた扉が開いたという一点だけで、妙な達成感が生まれてしまう。長期間放置された錆びついた扉を押し開けて、久しぶりに中に入った探検家のような気分である。元元元元彼女かよ。
さらに面白いのは、この一年半、理由が分からないまま閉め出され続け、そして理由が分からないまま突然受け入れられるという、強烈な非対称性だ。人は理由の分からない拒絶より、理由の分からない許可のほうが動揺する。拒絶されたときは怒りや諦めで処理できるが、突然許されると、どう反応してよいのかが分からない。まるで、ずっと既読無視してきた相手から、急に長文の連絡が返ってきたようなものである。
頭の中で思考が渦巻く。「なぜ今日?」「何が変わった?」「あの一年半は何だった?」と問いが浮かぶが、もちろん答えはない。サービス側から説明が来るわけでもない。こちらが勝手に経験し、勝手に困惑しているだけである。
とはいえ、一年半もログインできなかったにもかかわらず、重要なのはただ一つ。「今、入れる」。それだけで十分である。あの閉ざされたサーバーの門が再び開いたのだから、ここは素直に受け取っておけばよい。
ただし、一点だけ言えることがある。一年半の空白というのは、無視できない重さを持つ。人間の感覚としては、一種の「失われた年月」である。この期間を思い返しながら、突然戻ってきたアカウント画面を見ると、妙な違和感が生まれる。まるでタイムカプセルを掘り返したときのような感覚だ。開けた瞬間に、当時のままのデータが、静かにこちらを待っていた。
結局のところ、この一連の体験は、おそろしく単純な事実から構成されている。「一年半ログインできず、突然ログインできた」。ただそれだけのことだ。しかし、その単純さがかえって妙な面白さを生む。予兆もなく、理由もなく、説明もなく、ただ突然状況がひっくり返る。この不条理さこそ、インターネットという巨大なシステムに人間が振り回される典型例である。
そして今、ログインできたアカウントを前にして、こちらは淡々とその復活を受け入れるしかない。一年半の沈黙が急に破られ、向こうから何事もなかったように扉を開けてきた以上、もう深く考えても意味はない。扉は開いた。それがすべてである。
ダミーアカウントとの対比
一年半、本来のFacebookアカウントは沈黙していた。沈黙というより、こちらの呼びかけを完全に無視しているような状態といったほうが近い。ログインフォームに情報を入力するたび、どこか遠くのサーバーに仕舞われた自分のデータが「今日もダメです」と軽く肩をすくめている気がした。
それでも最初の頃は希望があった。サービスに不具合はつきものだし、明日には直っているかもしれない。ところが、その「明日」は永遠に来なかった。一週間が過ぎ、一ヶ月が過ぎ、季節が巡り、気づけば一年半。時間だけが淡々と積み重なっていく。こちら側の生活は変化し続けるのに、アカウントの扉だけは固く閉ざされたままだった。
その間、必要に迫られて作ったのがダミーアカウントである。必要といっても、特別な目的があったわけではない。ただ、「ログインできないあいだの仮住まい」が必要だっただけだ。ダミーアカウントは実家を追い出された大学生が一時的に住むマンスリーマンションのような存在だった。家具は最小限、荷物も最小限、とりあえず寝泊まりするには困らない。しかし「本来の家」とは比較にならない。居心地の根本が違う。
ダミーアカウントには当然ながら過去の投稿もなければ思い出もない。タイムラインは常にスカスカで、知り合いもほぼいない。誰もこちらを知らず、こちらも誰も知らない。職場の誰かが言う「Facebookで見たよ」の“Facebook”が、もう自分のものではない。その違和感はなかなか強烈だった。
それでも一年半も使い続ければ、奇妙な愛着が生まれる。ダミーアカウントは無機質なはずなのに、長く触れていると妙に人間味を帯びてくる。SNS のアカウントに対して「人間味」という表現は奇妙だが、使い続けることでこちらの癖や行動パターンが反映されてくる以上、どうしても人格のようなものが滲み出てしまう。
とはいえ、本来のアカウントとは比べものにならない。過去の写真、メッセージ、繋がり――それらが欠けた状態は、言ってしまえば「影のような存在」だった。そして一年半が経った。
ある日いつものようにログインを試すと、突然、門が開いた。
こちらは何もしていない。同じ端末、同じ操作、同じパスワード。ただ、いつも拒んできた扉が急に「入っていいよ」と言い出したのだ。予兆もなく、前触れもなく、あっけなく。本当にあっけなく。読み込みが数秒進んだあと、突然いつもの画面が現れた。
思考が追いつかない。しばらくは「これはダミーアカウントの画面ではないか?」と疑ったほどだ。だが、よく見ればそこにあるのは明らかに「本物」だった。一年半前の最後の操作がそのまま残っている。自分の投稿、自分の友人、自分の過去。ずっと閉ざされていた棚の扉が突然開いて、そこに昔の自分の痕跡が整然と並んでいた。
思わず背筋がぞくりとした。
対照的なのは、ダミーアカウントで過ごした一年半だ。この二つのアカウントが辿った時間の密度はまったく違う。本来のアカウントは、休眠状態とはいえ、過去の重みを抱えたまま時を止めていた。一方、ダミーアカウントは、軽い。過去がなかった分、何をしても痕跡が薄い。そもそも「自分が存在している実感」が弱い。
本来のアカウントにログインできない期間、ダミーアカウントは“代用品”としての役割を淡々とこなしてくれた。だが、そこにある時間は“仮の時間”だった。仮の住所、仮の名前、仮のつながり。生活に必要だから使っているが、それは本当の生活とは違う。“コピーしたレイヤー”の上で生活しているような、妙な薄さが常にまとわりついていた。
面白いことに、本来のアカウントに再びログインできた瞬間、この「薄さ」の正体がよく分かった。人は、SNSのアカウントに過去があるだけで安心する。古い投稿が並んでいるだけで「戻ってきた」という感覚が生まれる。誰がコメントしたとか、誰が写真に写っているかとか、細かいことはどうでもいい。その“積層された時間”そのものが、自分の生活の延長線にあるからだ。
ダミーアカウントとの比較は、まるで「ホテル暮らし」から突然「自分の家」に帰ってきたようなものだった。ホテルは便利だし必要なものは揃っているが、そこに“歴史”はない。壁の裏に思い出が眠っているわけでもない。長く滞在しても“宿泊者”であることに変わりはない。
対して本来のアカウントは、たとえ一年半閉鎖されていようと、そこに戻ってきた瞬間「帰宅」になる。過去の自分がそこにいて、時間の積み重ねが並び、そのまま続きを歩き出せる。
ではダミーアカウントでの一年半は何だったのか。
無駄だったかと言われれば、そうではない。むしろ非常に有益だったとも言える。仮とはいえ、SNS で“何も持たない状態”から生活する経験は貴重だった。つながりのないアカウントは、人間関係の騒がしさや不要な情報が極端に少なく、妙に静かだった。静かすぎて時々虚無すら感じるほどだが、その静けさはときに心地よい。
ただ、そこで過ごした時間は、どこか「自分の人生の別室」で流れていたように思う。本来のアカウントが本宅なら、ダミーは裏庭のプレハブ小屋のような場所だ。必要だから使うし、雨風をしのげるし、ときには便利だが、そこに住み続けたいと思うかと言われると微妙である。
そして今、本来のアカウントが突然復活した。
ダミーアカウントで生きていた時間が、急に「仕事を終えた一年半の代理人」のように見える。その代理人は文句ひとつ言わず働き、場を繋ぎ、こちらが帰ってきたら静かに身を引いた。ある意味、健気である。
しかしその健気さが少しだけ切ない。なぜなら、ダミーの一年半には確かに「時間」があったからだ。空白ではない。記録は薄くても、そこで実際に生活は進んでいた。
一方、本来のアカウントは一年半の間、止まった時計のように静止していた。そして今日、突然その時計が動き出した。止まっていたはずの時が急に繋がる。その感覚は、失われた時間の重さと、戻ってきた瞬間の軽さが同時に押し寄せる不思議な体験だった。
ダミーアカウントでの一年半と、本来のアカウントの一年半は、どちらも確かに存在した。しかし、その性質はまったく違う。一方は“軽い現在”が続き、もう一方は“重い過去”を抱えたまま眠っていた。どちらが良い悪いではなく、この対比そのものが奇妙におかしい。
結局のところ、この出来事はただひとつの事実に収束する。
――一年半ログインできなかったアカウントが、突然、何の前触れもなく開いた。
しかし、この単純すぎる事実が、驚きと滑稽さと妙な味わいを生み出した。ダミーアカウントで過ごした時間があったからこそ、復活の瞬間の衝撃はより強烈だった。
そして今、再びログインできた本来のアカウントを眺めながら、一年半のあいだ仮住まいとして働き続けたダミーアカウントに、小さく礼を言いたくなる。
以上