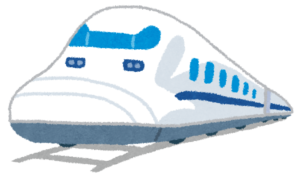単位はあげますから授業には来ないでください!(京都大学 豊田教授の言葉)
かつての大学教養部教授の名言「単位はあげますから授業には来ないでください!」の爆発力をとくと見よ!(日本の大学むかしばなし)
おはようございます。
2019年8月の今の令和の現代、偉そうに若人の学習の「コーチング」などをやっている筆者からの懺悔に似た記事を配信します。
筆者が大学生でありました、それも最初の2年間という「教養学部生」時代、専門学部に上がる前のモラトリアム時代においては、極めて面白い、現代では問題になること間違いない教員や教授がたくさんおりましたという昔話です。
大学は研究機関であり、そもそも「教育」などに力を入れていない、天才など「勝手に」育つ、ということで筆者の入った京都大学は、開学よりそのように嘯きつづけ、事実、国立大学最大の東京大学の概ね2/3の規模、学生数、でありながら、自然科学系ノーベル賞受賞者は日本で一番多い、という「実績」を何よりの拠り所として、自由放任の限りを尽くしておりました。
10,000人の凡人の学生の中に、1人だけ天才が混じっていて、それが世に出て立証されれば御の字、というような大学だったのです。
ですので、面白い教員はいても、教育者としてこれは立派だというような評価が高い教授というのは、とんといない、というのが通常運転でありまして、特に一般教養学部(京都市左京区の吉田山(吉田神社)の麓の吉田キャンパス)においては名物の教員がたくさんおりましたが、そのうち、究極的に有名かつ伝説になっている2名を、すでにこの世を去った先生方も天上からニヤニヤして見ているであろうと思いまして思い切りそのまま披瀝させていただきます。
まず、日本国憲法の豊田教授です。
最初の授業は、立ち見も含めてすし詰め状態です。
一目見ようと、そして彼の名フレーズを聞きにやってくるのです。
「国憲の豊田」こと日本国憲法の豊田教授。
「単位はあげますから授業には来ないでください!」
授業の冒頭にこのフレーズが炸裂します。
そうして、皆、このフレーズと共にぞろぞろと教室を出て行くのです。
「研究や講義の邪魔になるだけだから、単位だけ欲しい奴は授業には来るな」
という高尚な言葉が本当の意味だったのかどうか、当時も今も全くわかりませんが、噂を聞いた新入学生が1,000人以上登録し、初回の授業は毎回講義室があふれかえるほどの大盛況でした。
そして、決め台詞を聞くや否や、割れんばかりの拍手と大喝采。
控えめに見ても、こりゃあとんでもないところに来たもんだ、当時の筆者も驚いた光景でした。
筆者を含め、豊田先生を見たのは、この最初の授業(筆者は一番前の机のさらに前で体操座りをして見ました)だけです。
期末のテスト内容も、レポート課題のみ。
天から与えられる決められた答えを5行で書けば合格。10行以上書くと落第という謎のルールというかお作法がありました。
これで単位がもらえたのです。
最低点の60点(「可」の評価)ですが。
翌週から、講義の出席者はたった4、5人になります。
それでも、毎年数人は残る、というのが徹底したふるい落としに似て楽しい名物「講義(実際はワンフレーズですが)」でした。
そうして、先生は延々と黒板に向かってぶつぶつ会話しながら講義を進める、そんな授業風景だったということです(あくまで「伝聞」です。行ってないので)。
それでもこの日本国憲法は、「教員資格」を取るための必須単位だったのです。
どんな大学やねん(関西弁で申してみましたが、筆者の九州弁はついに卒業するまで修正されませんでした)。
続いて、名物教授として学内より学外で活躍された教養部数学の森毅(もりつよし)教授です。
愛称は、「モリキ」。
試験はなく、全てレポート提出です。
伝説として、そのレポートの束ごと、研究室の窓からバラまき、一番遠くに飛んだものから高い点数をつけて、真下に落ちたのは落第としたとか、レポートで紙ヒコーキを作って一番飛んだものを満点にしたとか、本当か嘘か作り話か全くわからない奇行の人でした。
この森毅先生、実は面白いことを言っていて、曰く、自分は冷静に物事をシラケて見ているけどシラケも一種の才能であり、思えば日本という国は、世界大戦中は戦争愛国青年ばっかりで、戦後になったら左翼革命戦士ばかりになり、それが同じ連中のままで丸ごと中身が入れ替わって面白い、もっと言ってしまえば、戦時中はお国のために尽くし、戦後は人民のプロレタリアート革命のために尽くし、そうして高度経済成長期になると今度は会社のために身を粉にして尽くすという、そんな周りに流されていつまでも自分よがりの熱い熱い国民ごっこをやっているよりは、シラケてそうした「さま」を眺めている方がよほど性に合っている、というようなことをおっしゃっていて、それもそうかな、と思わせるところがありました。
学生の方も相当「アホ」であり、モリキ先生曰く、レポートにカレーの作り方を丁寧に書いて、その通り作ったらうまかったから通した、とか、逆にレポートに「先生の単位を落としたら卒業できません。単位くれなかったら自殺します」と自分の血で書いてきた奴がおったけど、気持ち悪いから落とした、みたいな、令和の現代ならば社会問題になりかねないことも平然と言い放っておりました。
学生の方もアホです。
今更血判状かよ、というか、怖いでしょう。
おおむね昭和の平常運転、というか平成の初期の頃までは、これが笑い話で済んでいたおそろしく面白い時代だったのです。
そんな大学時代を送った筆者が、今は偉そうに「教育」を語り「コーチング」などやっている、面白いものです。
教育とは何か、これほど雄弁に語る事例もないと思います。
筆者は、昔話を懐かしむというだけではなく、このモリキ先生が遺した、「一方方向に熱中する」という特性は日本人は特に強く持っていると思っていまして、日本の歴史をざっと2,000年ほど振り返ってみましても
(赤文字は戦争国家、青文字は平和国家)
中国の漢書地理誌という歴史書に最初に書かれた百余国に分かれて相争う(戦国時代の様相)
から
卑弥呼による連合国家の成立と大和朝廷成立、クーデターを経て奈良の都で律令制完成
あたりで一気に平和国家となり、
平安京においては、国家戦闘力という概念すら消え失せ
と思えば
鎌倉幕府樹立で一気に軍事大国に「戻って」元寇を博多の波打ち際で撃退
そして室町幕府とかいう「弱い」政権を尻目に南北朝とか観応の擾乱とか、全然太平記の名前の世界ではない戦乱の世の中から、さらに戦国時代という世界でも類を見ない戦争大国へと成長を遂げ、
ついに国内の武力闘争に飽き足らず明国を平らげようと朝鮮出兵を行い(元寇の逆)
そして、戦国最終決戦の関ヶ原の合戦と大坂の陣
これにより江戸幕府による改易没収による大名恐怖政治により泰平の平和が訪れ、260年間に及ぶ平和な鎖国の世となり
明治維新で一気にまた帝国主義に目覚めて植民地獲得競争に乗り出し、維新よりたった30年で当時の世界最強の陸軍国ロシアを極東満州の荒野でハルピンまで押し戻すという驚異の粘り腰を見せ、そのまま軍事大国の道を歩んで昭和20年まで戦い続け敗戦
そして戦後は70年以上、平和憲法の国家として世界も二度見する経済発展を成し遂げる
---
という、目まぐるしく攻守思想変えて来ている、そしてそれをあまり苦にもしていない、稀有な民族なのです。
筆者の出身大学には、有名な近衛文麿さんという先輩がいて、この人は、日本の政治経済を裏から操り続ける黒幕として1,500年を生き抜いている「藤原本家」の筆頭近衞家の当主であり、天皇家に次ぐ家柄として当時の大日本帝国憲法下では昭和天皇も一目置く名家の御曹司だったわけです。
この人の、優柔不断と決断力のなさが、日本を大きく破滅の方向へ舵を切らせた主たる原因、因子でありまして、この人が間違って当時の(庶民人民に開かれているはずの)京都帝国大学などに紛れ込んでしまったことがそもそも日本国民の不幸の原因と考えております筆者より、不徳の先輩で申し訳ございません、とお詫び申し上げたいところです。
ちなみにモリキ先生の言葉をもう一つ借りますと、
「学生には4種類ある。一番偉いのが授業出てこんで出来るヤツ、偉い、二番目は授業出て来て出来るヤツ、それ当たり前、三番目は授業出て来ないしたがって出来ないヤツ、これは大多数、どうしようもないのが出て来てるのにでけんヤツ、とにかく情けないので4番目には入らんでなー」
というような、授業出てきているのに試験落ちた、全然出てないのに受かった学生がいるのに何でや、とクレームつけてきた学生に対して諭した言葉のようなものがありましたが、こんなこと、今の「プロセス重視」の大学において適用しようものなら週刊誌に書き立てられて速やかに大炎上、という流れになってしまいそうで、それはそれで大衆のおもちゃになりそうで怖いなとも思います。
モリキ先生は1957年京都大学教養部助教授に就任されます。
そして1971年、教授昇任の審査の際に、助教授就任後の数学者としての業績は論文が2本だけだったため、「これほど業績がない人物を教授にしてよいのか」と問題になったが、「こういう人物がひとりくらい教授であっても良い」ということで京都大学の教授となった、とあります。
筆者の法学部のゼミの恩師は刑事訴訟法の鈴木茂嗣教授でありましたが、この先生も、「司法試験に受からなくても司法試験委員になってしまった」と述べる面白い先生でした。
先生にあやかって、筆者も(旧)司法試験受からないでおきました!
というのは冗談ではなく実力だった筆者からのむかしばなし放談は以上です。
(2019年8月8日 木曜日)
▷▷次の記事は