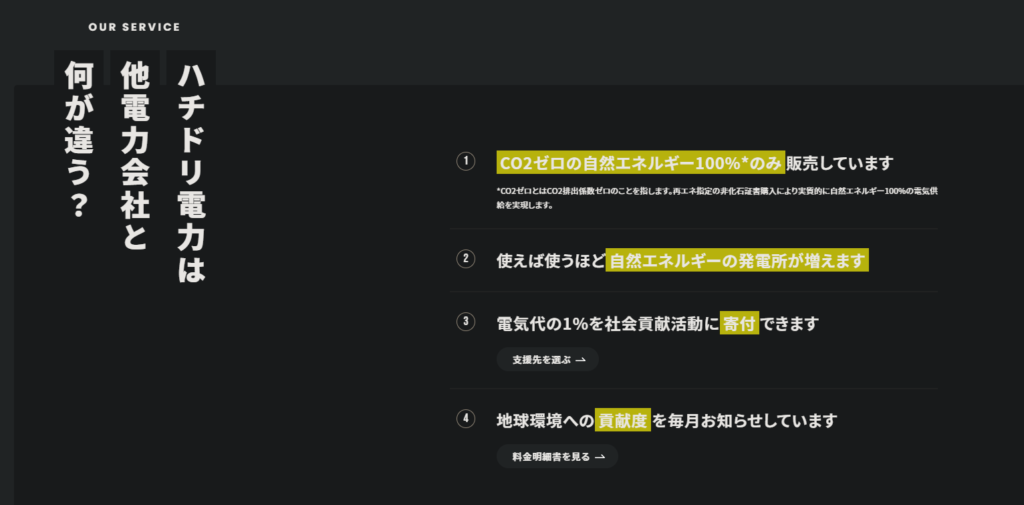出光興産に見るティール組織
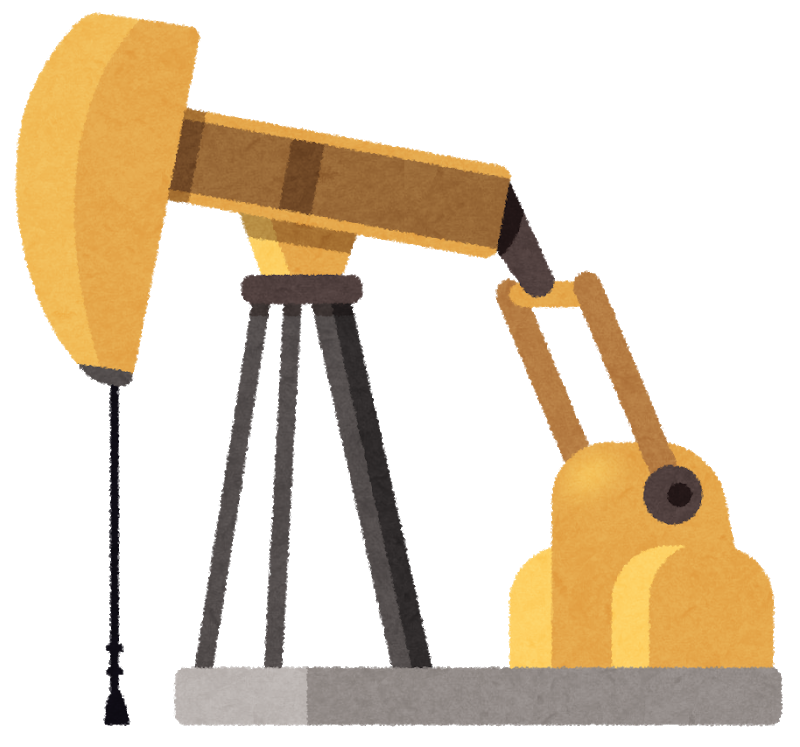
出光興産に見る我々が目指すべきティール組織についての意思決定の考え方について
おはようございます。
2019年(令和元年)6月の、会社の意思決定を究極までスムーズに行うためにはどのようにすれば良いかということを論じてみたい筆者からのブログ配信記事第二弾です。
究極的な理想形態として、グリーン組織を超えた「ティール組織」の一つの究極的な形として、役職員一人一人が、完璧に会社を代表して最終意思決定を下し、その会社意思決定は代表取締役の職責にある者にも覆すことができない、という訪日旅行会社株式会社FREEPLUSの取組み事例をご紹介したところ、多くの質問やコメントをいただきました。
別段、同社と取引上の関係があるものではないところ、企業経営の事例として非常に注目しておりますので、もう少し論を進めてみたいと思います。
エージェンシーコストと言われる問題があります。
株主が企業経営を、取締役会に委ねて、取締役会は、権限規程に基づき、会社の各執行役員に執行権限を分散して移譲し、そうして各執行役員が所管する本部は、複数の部によって構成され、部には部長がいて、その部の中にいくつかの課があって、課には課長がいて、それぞれ、分散され移譲された権限の中で日々の業務執行が行われている、というのが通常の会社組織の在り方だと思います。
しかしながら、あくまで、これは担当者が通常の業務執行を行う場合に限り、会社としての行為であることが「擬制」されているに過ぎず、会社の、権限規程の一覧表に記載されるような、会社としての契約行為や多額の借財、もしくは人事上の重要な使用人の決定に関するような事項は、その行為の「軽重」に応じて、担当部長決裁、担当役員決裁、それから経営会議や取締役会といった合議体での決定や稟議を要するもの、もしくはコンプライアンスを統括する法務部門や外部顧問の(大抵弁護士で構成される)第三者委員会の諮問結果を踏まえて判断されるべきもの、そしてその判断した内容は議事録の形で文書に残しておくように、といった段階をとるのが普通です。
しかし、どこまでが、担当者で決められて、どこからが「部長決裁以上」といった承認決裁行為が必要とされるかということについては、結構曖昧であり、会社ごとの権限規程表を全て諳んじている人間など筆者も見たことがありません。
見たことがない、ということは、本来は、会社としての意思決定というのは、関係する担当者が全て決めるべきことであり、そして、そのゼロ秒で決めることができる意思決定のプロセス上、他者の助言を得るという検討機会が必ず必要になるという、それだけのことなのではないかと考えるのです。
そうして、全ての担当者は、その担当事項に対して、最終的な会社意思決定を行うことができる、しかし、その会社意思決定を行うためには、その意思決定に影響を受け、束縛されることになる関係部門や関係担当者に助言を仰ぐ、助言プロセスを経る必要がある、そしてその助言プロセスをどこにどう求めるかについても、その意思決定担当者に全てが委ねられている、という形態が提示されることになります。
これこそ、承認0秒の、究極的に意思決定の速い(というか承認行為というものが存在しない、あるのは助言プロセスにおける検討時間だけでこの検討時間というのは極めて重要)組織が出来上がるというわけです。
承認にかかる時間は無駄と思われますが、真面目に検討する時間や専門的知見を持った者のアドバイスに従い考え直すという、検討プロセスについては、非常に組織的意思決定において重要な意味を持つものと考えています。
そこでの助言プロセスを経た実質的検討結果こそが、その場面における、会社としての最高の意思決定を唯一導き出すことができる、最良の方式でありメンバーである、ということはかなり正確に正しいと思われるのです。
この、承認ゼロ秒の組織運営を紹介したときに、現役の企業経営者からは、とても興味はあるけれども、とても勇気がいる、というコメントを頂戴しました。
その通りだと思います。
それから、このような意思決定の仕組みを導入した瞬間、例えば東証に上場しようとした際に要求される会社の各種規程類が、そのほとんどを廃止することになることから、上場はこの仕組みを導入した瞬間諦めなくてはならなくなるということに繋がります。
上場した場合に登場する、一般株主や銀行等の既存債権者に対して、説明がつかないというわけです。
ところで、これと同じような意思決定の仕組みと機構を持つ会社が、かつて、筆者が知る限りでは一つだけ、歴史上にあったような気がしています。
それは、上場する前の、戦前から活躍した出光興産、その会社です。
筆者が社会人として銀行に入った1997年(平成9年)当時、出光興産はサントリーと並んで、非公開企業、つまり同族企業の最大手の一つでした。
そして、銀行の出光興産担当の当時課長代理であった、ある意味めんどくさい先輩に、独身寮の風呂や食堂でつかまったときに、たびたび聞かされたこの会社の社是は、「和(やわらぎ)」というものでした。
驚くことに、この社是により、出光興産には定年がない、もちろん解雇もない、そして組合もない、という特異な大家族主義であり、そこには労使関係など存在しないという、そういう前提だったのです。
ほとんど覚えていないのでうろ覚えで書くのですが(これを見て詳細なエピソードがわかるという方は遠慮なく筆者をつついてもらいたいです)、同社のある油槽のトラブルがあり、工場全員でつきっきりで作業してその対処にあたり、幸い事故に至ることはなかった、ということがあり、会社(の人事部)がこの献身的な対処対応に対して現場の部隊に報奨金というか慰労金、ボーナス(残業手当的なもの)を支給しようとしたところ、現場は激怒して、ただ現場で必要となることを為しただけあり、そんなものを受け取るわけにはいかない、出光人は金で転ぶようなそんな人間ではない、舐めるな、と拒否した、というような話です。
筆者は銀行員として、しかも産業銀行(日本興業銀行という長期信用銀行)という特殊な銀行に入って、それこそ会社はマニアというくらいたくさん見てまいりました。
取引先の会社ごとに一枚紙で作る「会社要項」というものを、それこそ、何百枚も作ったり、見てきたりしたのです。
そんな筆者が、直接担当したことがなくても、この話一つをもって、出光興産という会社を強烈に印象付けており、こうして駄文にも書くのです。
日本は誰も責任を取らない社会であり、会社の意思決定も不透明で、映画シン・ゴジラ(2016年東宝)においても、うちの国(米国)は大統領が決める、おたくの国は?などと聞かれて答えに窮する官房副長官臨時代理や内閣府特命担当大臣などが描かれておりますが、この方式だと社員みんなが当事者になるので、それが嫌な人には即辞める理由になりますし、「俺は聞いていない」といったダメな上司や上役というものも存在が一切許されなくなります。
なぜならば、助言を求められる存在になるためには、それなりの組織貢献という振る舞いを行っておかなければならず、そうした業務上の評判がない人は、助言プロセスに入れてもらえないのです。
顧客からのクレームでも悪い報告でも、即情報は聞きたくなり判断の材料にしたいと心から思うことになりますし、起こったことで責任転嫁するより、起こったことに対するこれからの対応こそが本当に大切であることを学ぶことができます。
また、これが一番重要なのですが、助言プロセスの存在により、担当者や社員一人が抱え込んで腐らせる、という日本企業の悪いところが瞬間で改善されるのです。
筆者は、GAFAとか言われる巨大なプラットフォーマーに対して人間の組織体であるところの中小企業が勝てるとすれば、このような「承認行為」の無駄を極力省き、実質的な専門知見を集めた「検討」時間にフォーカスすることだと本気で考えております。
よって、この承認不要の、FREEPLUS社の今後に大いに期待するとともに、自社においても、少しでも取り入れられるようにしていきたいと考えています。
人生はいつだって最高ですね。
こちらからの宣言は以上です。
(2019年6月23日 日曜日)
▷▷次の記事は