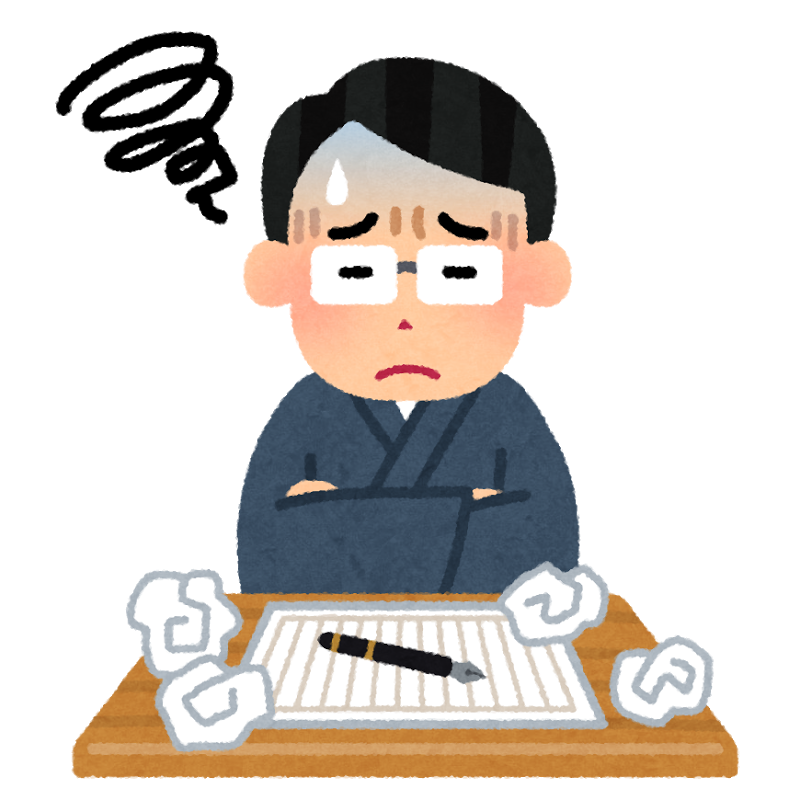デジタル時代における印税の仕組みを考察して書く意欲を高めたいお話
おはようございます。
2017年3月のデジタル時代の出版に関する考察記事です。
売れない著者からの取らぬ狸の皮算用な話です。
デジタル時代となり、著作物もこれまでの紙の形から、デジタルな形に移行して来たように思います。
本を買うのであれば、電子書籍という方もいて、スマホなどのデバイス端末で本を「読む」人も増加の一途だと思います。
ところで、この本を電子書籍の形で出す場合、これまでの紙で出す場合とは異なる印税についての取り決めが非常に面倒になってくるので、あらかじめ言及しておいた方がよさそうです。
なぜならば、ひとくちに電子書籍と言っても、その電子化の方法にはいくつかの方法やフォーマットがあるからなのです。
紙の本であれば、原稿の、そして印刷されて製本された本も、種類は一つだけで、その後文庫になったときは文庫版になったり、新書版になったりする程度であることは想像できると思います。
しかしながら、同じ「本」を電子書籍で出そうとしても、どの電子書籍の媒体に乗っける電子書籍にするのかをまず選ばないといけないわけです(書き方が面倒です)。
アマゾンだけが電子書籍やってるわけではない
電子書籍といえばアマゾンやろ?と言われる方もいらっしゃるかもしれませんが、確かにアマゾンのキンドルが現時点での世界の最大手の電子書籍出版元だと思いますが、iBookもあるし、ソニーや楽天の提供しているファイル様式もあるわけです。
さらに、同じアマゾンのキンドルであっても、iOS上で動くのかアンドロイド上で動くのか、ウィンドウズのPC上でも動くのか、というOS上の相性もあり、簡単ではないのです。
まだまだ電子書籍は百花繚乱の若い業界であり、プラットフォームは乱立していますので、とても個人レベルで対応することはできません。
どうせアマゾンやろ?と思ってアマゾンだけに対応していたらどうなるか。
これぞアマゾンの思う壺になってしまうわけです。
みんな、いつしかアマゾンがなければ生活できなくなるわけで、生活の根っこのところをキンドルやアマゾンに握られるという裏寒い状況になってしまうかもしれません。
とにかく、リアルな紙の本を作るという作業は数百年の業界としての歴史があって、やり方もかなりの部分統一化されていますが、電子書籍については、ここ10年で急速に広まって来たものであり、紙の本を製本するより現時点では非常に面倒で標準化されていないということはわかってもらいたいというところです。
印税もバラバラと面倒になります
さらに、本が売れた場合の大事は儲けの分配、いわゆる印税についても面倒です。
紙の本は、印刷もしくは増刷した時にしか、著者に印税は支払われません。
世の中に、その著作物を生み出した冊数に応じて、印税がはいるわけです。
一括払いのようなものです。
しかし、電子書籍は、一括して発行するという業態をとりません。
読者が買う(ダウンロードする)たびに出版(印刷)したことになります。
なので、出版元は、電子書籍が売れたたびに、その印税をこちょこちょ計算して、著者にある一定の間隔で支払い続けていかなければならないのです。
これは、非常に面倒です。
もちろん、著者側としては、昔書いた本からの印税がちょこちょこ将来にわたって入ってくるのはありがたいのですが、書いた本人すら忘れていた小額の振込がなされてきても、それを申告していくのもかなり面倒なことではあります。
最初の一回で済ませたいという気持ちもあります。
売れた分の電子書籍が、それぞれの電子書籍のフォーマット別に、別の出版元から、ちょこちょこ、一ヶ月分とか三ヶ月分とか半年分とか期間もばらばらのまま、ランダムに振り込まれてくるというわけです。
それをまとめて申告しなければなりません。
とっても大変です。
さらに、紙の本とはちがって、最初の一ヶ月は99円、なんという売り方も平気でやる商品ですから(原価とデリバリーコストが少ないとみなされる、また電子書籍フォーマット側も、よく読まれる有名書籍はうちしか見れないと宣伝したがる)、単価もばらばら、納期もばらばらの、ばらばら小額振込がちょこちょこされて、もはや筆者も著者も混乱の極みということになるわけです。
原稿料として買い取ってもらった方が楽なのかもしれません。
著作権は相当期間長い期間つづきます(著者が死んでから原則50年)ので、仮に著者がなくなってしまった時でも遺族に対する印税の振込義務は継続します。
したがって、相続が発生するとさらにややこしくなるのです。
それでも、これだけの事務手間を考えても、個人の権利を守る方向は進んでいくことになるので、こうした煩雑な事務手間を削減する手法や考え方もまた待たれることになりそうです。
著者の死後も増刷されるような本を書くのが目標の筆者の無用な心配を杞憂と呼ぶらしいですが、とりあえず印税の話でした。
ベストセラーになった時の心配だけは十分すぎる筆者からは以上です。
(2017年3月8日 水曜日)
▷▷次の記事は