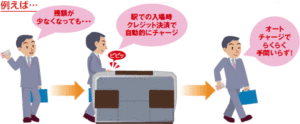ポケモンGOという任天堂コンテンツが巻き起こした全国的な社会現象
 |
| 違いがわかりません… |
おはようございます。
2016年7月のコンテンツに関する配信記事です。
昨今、日本全国でポケモンGOが席巻しています。
久しぶりの全国的フィーバーです。
これは筆者が小学校の時に体験した初代・二代目ドラゴンクエストのリリースの時に匹敵する社会現象ではないでしょうか。
しかも、今回は親世代もフィーバーしています。
私と年の頃が同じようないい年したおじさんが、「よっしゃピカチュウゲット!」みたいなことを堂々と街中でできる世の中になったわけです。
日本のアニメやゲームが数十年かけて市民権を得て世界に雄飛したことを改めて感じたようで感慨深いものです。
花札会社と呼ばれた任天堂という会社
任天堂というメーカーは、花札などの遊具を作っていた京都のメーカーでした。
この会社が、ファミリーコンピュータ(ターと伸ばさない)という世界を変える家庭用ゲーム機をリリースしてからゲーム市場は本格的に始まり、そして現在はスマホやソーシャルゲーム全盛の時代となりました。
ドンキーコングやバルーンファイト、そしてツインビーなどをやり込んできた昭和世代の者からすれば隔世の感がいたします。
しかし、ゲームの世界も、RPGで物凄い謎解きにはまる難しいものから、結局ポケモンGO(ゲーム運営は別会社ですが登場するキャラクターはあくまで任天堂商標のものという意味で)的な親子で楽しめる簡単なルールのものに収斂してきているような気がいたします。
約30年以上かけて、結局体験型の、親子で楽しめるファミリータイプのゲームが世界中で流行るというのは不思議な気もいたします。
ポケモンGOというゲームは基本的には「ひたすら歩く」「ポケモンを捕まえる」のみです。
人間の速さで移動することがカギのようで、電車や車での移動はあまり得策ではないようです。
せいぜい自転車で走り回るくらいなのでしょうが、それならば歩いたほうが安全だし結局早いようです。
歩いて「ポケストップ」「ジム」「ポケモン」といった場所やキャラクターを探してキャラクターを集めるというゲームです。
ゲーム上の地図ではなく、リアルな場所とリンクしているのがこんなに面白い、人を熱中させるものだとは思いませんでした。
さて、本当に書きたいことは別にあるのですが、前段で長くなりすぎたようですので、続きは次回とさせていただきます。
早朝ポケモンハンターの筆者からは以上です。
(注) 読者のご指摘あり、ポケモンGOは任天堂ではなく、Nianticというアメリカの会社が運営しており、あくまでも登場するキャラクターが任天堂商標であるということがわかるように記事を修正致しました。
(平成28年7月27日 水曜日)