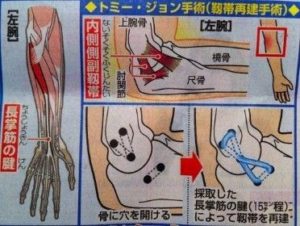[論考]とりあえずまずは始めてみるという柔軟性が極めて大切である
 |
| 本文とは関係ありません |
おはようございます。
2015年3月の柔軟性に関する配信記事です。
世の中高度に専門化されておりまして、一体なにが受けるかわからないようになっております。
お笑いの世界でも、ラッスンゴレライという何の意味もない呪文のようなコントが小学生高学年の間でばかうけしておりますし、ケンダマクロスという、プラスチックと鉄心入りのけん玉が小学校低学年に大人気となり、学校の「生活」昔あそび授業で鉄板の縄跳びや鉄棒に並ぶ勢いでけん玉名人が輩出されたり、世の中不思議なものです。
これを見てわかるのは、質より量が大切ではないかということです。
何が読者に受けるのかわからないと言っていた漫画の神様手塚治虫は、とにかく多作でした。
締め切り前になると、手塚先生の原稿を待ち続ける各漫画誌の編集者がイライラしながら待機するというのが風物詩だったらしいですが、手塚先生は自らの作品の半分はそうした編集者のプレッシャーのお陰であったと述べておられます。
多作にするため、自分の能力を限界まで絞りだすために、外からの連続締め切りという圧力を利用したのかもしれません。
頭の中の大作は世に出ることはない
『最後の一葉』 (The Last Leaf) 、『賢者の贈り物』(The Gift of the Magi)といった名作短編で知られるオー・ヘンリーの作品に、類まれな能力を認められ超話題となる画作の構想を発表した画家がいましたが、その作品を手掛けることをなんのかんのと理由をつけて遅らせた結果亡くなってしまい、彼の作品は、誰の目にも触れずに彼とともに埋葬されることになった、というものがあるそうです。
同じ画家でも、最後の一葉を描いた画家との違いは、まず始めたか否かということなのでしょう。そして、それは決定的な違いになるのです。
そういうことですので、そろそろ下手なブログでも始めてみようと思います筆者からは以上です。
(平成27年3月18日 水曜日 平成28年3月18日 金曜日)
▷▷次の記事は