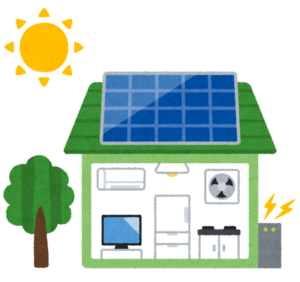(2019/08/26)ついに夏休みが終了(親の自由解放宣言!)したこととご飯を美味しく食べるお櫃(おひつ)の話です
おはようございます。
2019年8月の、子供達の夏休みが終わって親としての重労働から解放されてヒャッホーな筆者からの配信記事です。
夏休みといえば、筆者が小・中学生やっていた頃は8月31日までまるまる8月は夏休みだったところ最近は冷房器具が小・中学校に設置されてきたこともありまして、また学校週五日制が浸透したことに伴い、各都道府県や市町村によりますが、8月の後半になったら、要するにお盆が終わったところから本格的に登校モードになるというのが今の令和の時代のスタンダードのようです。
長きにわたる夏休みを共に生き抜いた、保護者のみなさま、誠におめでとうございます。
感慨もひとしおだと思います。
子供たちを学校なりに「収納」でき、さらに公立小中学校においては、「給食」の支給があるというのは、本当に親としてありがたいことであり、改めて、日本の「義務教育」というもののありがたさに感謝の気持ちが湧き上がってまいります。
この「初心」を忘れずにいきたいものです。
さて、そのような慌ただしいご家庭の「朝」において、和食中心の家庭で朝食を取る際に活躍するのが、「お櫃(おひつ)」です。
日本人として、やはり(糖質制限などという風潮もあるものの、明らかにパンに代表される小麦系食事よりは腹持ちがする気がする)「炊飯」にはこだわりがありまして、筆者については、はるか昔に炊飯器でご飯を炊くことをやめて、直接釜でご飯を炊くようになりまして随分経ちます。
炊き方は簡単です。
ティファールなどのメーカーが提供している土鍋系の蓋付き鍋を買ってきて、水を張って吸水させて炊くだけです。
さて、炊きたてのご飯は大変美味しいのですが、そのまま土鍋に入れておくと、水分が飛んでしまって色艶が落ちることがネックでした。
そんな中、知り合いに「お櫃」、それも最近は木やプラスチックではなく「陶器」「磁器(セラミックス)」のお櫃が出ていて結構いいということを教えてもらいましたので、早速調べてみました。
炊いたご飯をすぐにお櫃に入れて、夏ならば冷蔵庫、冬ならば常温で保管しても、1日程度なら十分保管でき、さらに適度に水分が持続するので、ご飯が固くならずに、食べるときにはそのままお櫃ごとレンジでチンして温めるか、食べる分だけ茶碗に取り分けて温めることで、炊きたてに近いおいしさに戻ります。
これは、炊飯器の保温機能を利用する、または炊きたてのご飯を小分けにして冷凍庫に保管する方法に比べて、はるかにエコであり電気代を節約できますが、何より炊きたてに近い味をかなり長い期間実現することができるという利点があります。
これまでは、余ったご飯で1日以内に食べるものは、茶碗にラップをかけて冷蔵庫に保管していたのですが、これではラップの内側に水が垂れてきて、少々汚い感じがしておりました。
この、陶器のお櫃だと、適度に陶器の裏側が濡れていますが、レンジで温め直すといい塩梅に米に戻って、ご飯に戻るようです。
早速、筆者も手頃な茶碗にご飯をよそって、同じ茶碗を上から反対側に重ねることで、しばらく炊きたてを保管しておいたところ、十分な効用を確認いたしました。
そこで、磁器のお櫃を買おうかと検討したのですが、どうも、自分としては「蓋(フタ)」がガラスのものはないかと探したのですが適当なものがありませんでした。
個人的にはフタがガラスの方が、中身を確認できるので、一体中身があるのかないのか、洗っているのかいないのかいちいち蓋を開けなければならないというのがネックだったのです。
しかし、「炊飯器」で蓋がガラスのものはありましたが、筆者が調べたところでは、蓋がガラスのお櫃を探すことができませんでした。
そこで、手元にあるもので代用することにしました。
それが、上に示しております写真の通りです。
磁器の深皿の入れ物に、普通の両手鍋で使っていたガラス蓋だけが残っていたものをあてがい、即席のお櫃としてみました。
これは、ガラス蓋にステンレス金具が使われているので、そのまま入れてレンジで温めることはできませんが、温めるときは蓋をとるか、お茶碗に取り分けて温めればいいわけです。
この即席お櫃は、丸々3合入れるとご飯が蓋につくほどパンパンになるので、3合炊いたら二人分くらいを茶碗によそって、余った分をおひつに入れるとちょうどいい塩梅(あんばい)です。
ちなみに、食事中にテーブルに置いておけるので、おかわりの度に席を立たなくていいですし、なんだか料亭や旅館での仕出しのようでテンションが上がりますが、その分どうしても食べ過ぎてしまうようです。
このように、なかなか一度には食べきれないご飯ですが、塾帰りや残業や部活動で帰りの遅い家族にできるだけ温かい炊きたてに近いご飯を食べてもらうのはいいことだと思います。
お米がうまく消費されれば、全体の食費も抑えられて家計にも助かると目論んでおります筆者からのコメントは以上です。
(2019年8月26日 月曜日)
▷▷次の記事は