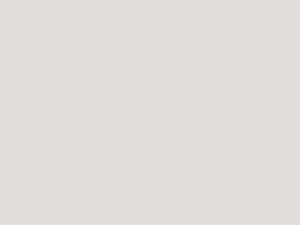(2019/07/04)日本の小中高教育が硬直化して時代に合わなくなってきているのではないかと思う話です
おはようございます。
令和元年(2019年)7月の、梅雨前線による大雨災害が南九州を直撃しているという中に配信させていただきます今日のニュースです。
日本の小中高教育が硬直化して時代に合わなくなってきているのではないかと思う話です。
今の時代、座学の教材で、先生1人が黒板の前に立って、「講義」するという授業形式って、もはや150年以上続いている姿ですが、もうこのマルチな世の中には合わなくなってきていると思うのです。
ATAMA PLUS(アタマプラス)という教育ベンチャー企業が提供するAI型タブレットアプリによる(機械が提供する細切れ単元の動画講義と演習テスト)による個別講義による学習成果の方が、こうしたスクール形式黒板型講義と「宿題」「復習」との合わせ型で行う授業形式に比べて、格段に理解が早く進む、というのは、実際に中学数学の体験学習をこのアタマプラスでやってみた筆者でも実感していることですし、実際、2018年5月末時点でこのアタマプラス教材を導入している塾や予備校は日本全国で100程度だったのが、1年後の2019年5月末には500以上に急増し、さらに教材の提供やインストールが間に合わず、150教室程度の順番待ちの状態になっているというような話を聞くにつれ、一人の教諭がクラス35人以上の「平均的」「最大公約数」的な講義を行うという授業形態、それから演習についても、個別の理解度や深度、進度に関係なく「基本的に同じレベル」の問題を与えて解法を提示するというのはもう非効率ではないかと思うのです。
筆者も、遠い昔のことになりましたが中学校や高校時代におきましては、自ら「聴く」科目の授業と「内職」する科目の授業は峻別しておりまして、かつての昭和の名残がある授業の中では、例えば日本史の授業で「そこはわかっているから」筆者の中では飛ばして世界史の自習をしていたところ、同じ山川出版社の教科書でも色が違う(日本史は赤で、世界史は青)ことを咎められ、要するに罵倒(に近い強い口調)で怒られたというような経験を持っておりますが、そんな授業態度による教諭の評価などを気にしていたら、3年間しかない公立高校の進度の遅い授業で、中高一貫ですでに最後の2年間は浪人しているくらいの授業進度のライバルたちに太刀打ちできるわけないだろうと「判断」してそのままで通しました(当時のセンター試験の日本史の得点率は93%でした(3問不正解)。英語の方がよほど不得意でした)。
おかげさまで、職員室においてはあまり評判の良い生徒ではありませんでしたが、自分の教育は自分の責任と割り切り、他人の評価など関係ない、大学行くのは自分だ、と決めていたので、学校の提供する「授業」その他の膨大な時間的拘束からかなり自由に過ごすことができたというわけです。
逆に、学校の授業が終わった放課後になったら、空いた教室や特別教室を利用させてもらって、思う存分自学自習ができる環境を提供してもらいました。
その点は非常に感謝しております。
さらに、職員室の進路指導の教諭のところに届く、各種模試(進研模試や旺文社模試、各大手予備校の提供する、例えば駿台予備校の全国統一模試など)の教諭向けの詳細かつ膨大な解説が附された解答集などを無料で借り受け、そのまま受験試験対策として活用できたのは、筆者が全日制高校に行った何よりの「価値」でありました。
学友が、部活の最後の大会が終わった中、予備校や塾に消えていく中、学校に逆に居残り、社会科自由室といった適当な空き教室を占拠して、職員室から虎の巻を借りて読み込む、あまつさえコピーもとってしまう、というわけです。
ですので、全てをネット授業の動画配信にすれば良い、と言っているわけではありません。
リアルな学校というファシリティやコミュニケーション環境や卒業生とのアクセスなど、使える便利かつためになる資産もたくさんあり、何より全日制学校に「通う」ことで生活のリズムも取れますし、運動もできて一石二鳥です。
ただ、学習者個別の事情に応じた、オーダーメイドの教育方針やカリキュラムが提供される技術的発展に背を向けて、黒板背にしたスクール形式「のみ」で授業が進むことに強烈な違和感を感じているだけの話です。
どんな「神」授業を聞いても、自分の手を動かし頭を働かせて演習や問題を解かないことには、真の学力は身につきません。
そういう意味で、自学は家に帰ってから、学校は講義だけ、(そしてたまにまとめてテスト)という自宅と学校の住み分けが問題だと考えているのです。
筆者は、50分一コマの授業時間が与えられているのであれば、20分を知識吸収のための公立的な動画講義を利用したインプットの時間にあてて、残りの30分でその知識を利用した演習問題に取り組み、わからない場合にどこに戻れば良いかを個別に教師がそれぞれの学生に伝えてあげるという「指導」の方式が最も全ての学生の満足度が高まる授業の方法だと思っています。
本日も雑駁な議論になりましたが、教育という多大なコストがかかる問題についてもっと真剣に具体的な改善策を出していかなければならないと強く思っております筆者からの記事は以上です。
(2019年7月4日 木曜日)
▷▷次のページは