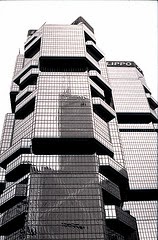長期信用銀行という特殊な銀行があった時代を振り返りたいと思います(日本興業銀行のはなし)
 |
| 写真は台湾銀行。戦後の長期信用銀行の母体となりました。 |
おはようございます。
2014年4月の銀行に関する配信記事です。
説明しよう。で始まるアニメ「ポケットモンスター」の世界に倣い、既にお話した銀行の世界を深堀りし、その中の構造までフォーカスしていきたいと思います。
日本における銀行ですが、詳しく言いますと法的な区分だけでも幾つかに分かれます。
法的には、銀行法に基づく銀行は「銀行」と呼ばれますが、他にも、日本銀行法に基づく「日本銀行」は銀行の銀行として、「円」という通貨の流通と物価の安定を担っている中央銀行ですし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律によって信託業務の兼営の認可を受けた「信託銀行」という兼業銀行もあります。
そして、21世紀に入って滅びてしまいましたが、かつて「長期信用銀行」という銀行もあったのです。今回はこの銀行サブカテゴリー業界についてお話します。
長期信用銀行という業態の銀行があった
長期信用銀行とは、比較的短期に引き出される場合が多い預金の預入によって資金調達を行う通常の銀行とは違い、比較的長期の債券(文字通りの券面)を発行することで資金調達することを当局に認められた特殊な銀行です。
割引金融債、利付金融債といった券面を発行し、その販売代金として資金の流入を行います。
この割引金融債や利付金融債を、ワリコーといったりワリチョー、ワリシンといった愛称で広告宣伝し、銀行の店頭で「販売」しておりました。
店頭で販売する以外にも、資金運用の一つとして、地方金融機関にも定期的に売りさばき、都市銀行に匹敵する資金調達力を有していたのです。
つまり、貸金が伸びない地方銀行の資金運用先として、これら長期信用銀行が発行する割引債や金融債が、一定の重要な役割を果たしていたというわけです。
そうして、支店網を拡充することに非常に強い規制を受けた長期信用銀行は、そうした地域ローカルに店舗網を持ち潤沢な預金等の資金吸収力を有する各地の地方銀行とタイアップして、預金による資金調達と企業個人向け貸し出し融資をすべて自前で行う都市銀行に対抗していたのです。
ここで、どうして預金の預入を行う銀行と債券発行を主とする長期信用銀行が並立したのかといいますと、戦後から高度経済成長に至る時代における通常の預金での資金調達手段では、いつ引き出されてしまうかわからずそのリスクヘッジの方策がなかったので、通常の銀行が長期の資金貸付を行いにくかったという事情があります。
すなわち、5年以上といった長期固定金利の貸出を起こすことが難しかったのです。
この点、例えば利付金融債は5年ものの固定金利で販売していましたので、ちょうど企業向けの貸出も5年間の固定金利にすれば、銀行の資金と金利の流れはちょうどマッチするというわけです(むしろ短期貸付のほうが困るくらいです)。
ですので長期信用銀行という業界は企業の設備投資などの長期での資金回収を必要とする部分で必要とされたわけです。
しかしながら、そうした構造に大きな変化が訪れます。
金融の自由化が業界秩序も流動化させ果てしない再編へ
金融の自由化により銀行業界内でのインターバンク市場が活性化され、固定金利で貸し出しているローン債権の金利部分の交換(スワップ)が簡単できるようになってきました。
さらに、ローン債権そのものの売買(パートアウト、パートインといいます)すらできるようになっていった結果、長期固定資金を調達し貸出を行うという長期信用銀行自体の存在意義が薄れていったのです。
さらに、企業の設備投資に回す長期固定貸出のニーズが、資本市場の高まりによる他の資金調達手段(増資や社債発行)に取って代わってきたというのも大きいです。
かような「時代の流れ」の中で、長期信用銀行はその役目を終え、静かに市場から去ったわけですが、そのような時代の最終コーナーに身をおいていた筆者などは時に懐かしく思い出すのです。
日本債券信用銀行(現在あおぞら銀行)
日本長期信用銀行(現在新生銀行)
そして、三兄弟長男格の 日本興業銀行(現在みずほ銀行)
今日は少々難しいお話になってしまいました。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
ポケットモンスターには疎い20世紀少年からは以上です。
(平成26年4月4日 最終更新:平成28年4月4日 月曜日)
【関連記事】