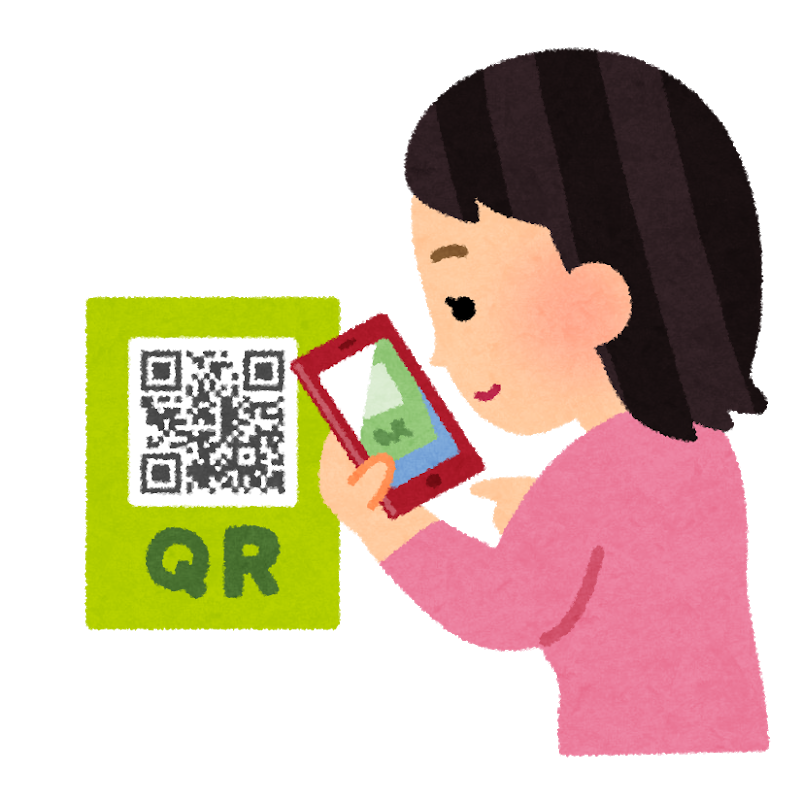PayPay祭りが終わってみれば家電量販店の商品の値段がちょうど2割落ちる価格随時変動の日本というQRコード決済が全く進まない国のお話です
おはようございます。
ブログ「ビルメン王に俺はなる!」を主催広告運営する管理人兼筆者です。
2018年12月の家電量販店の商品値段設定が日と時間によって刻々と変わっていく時代になったという配信記事です。
2018年の12月の歳末セールに合わせて、PayPay祭りというものが日本を一時的に席巻し、100億円という販促費の大盤振る舞いに日本中のポイント愛好者たちが殺到したお祭りがありました。
すなわち、モバイル決済サービス「PayPay」のリリースに合わせて行われた販売促進作である「100億円あげちゃうキャンペーン」が、12月13日午後11時59分で終了したのです。
キャンペーンは、支払い額の20%か、最大10分の1の確率で全額をポイント還元するという内容でした。
還元率の非常な高さからネット上でも注目が集まり、12月4日のスタート直後からTwitterなどのSNS上では、高額商品を購入し、全額還元が当たったというユーザーの投稿が目立っていました。
結局、2018年12月4日にスタートし、来年3月末までを一応のキャンペーン期間とし、還元総額が100億円に達し次第終了するとしていたものですが、開始よりちょうど10日間を経過した12月13日に還元総額が100億円に達したと、運営元のPayPayが同日午後10時に発表し、めでたく終了の運びとなったというわけです。
しかしながら、この高額商品購入、のところにからくりがあったようです。
一部の家電量販店などでは、この高額商品の値段が、PayPay祭りが終了した直後より大幅に、だいたい20%程度すっと「下落」したという報告がちらほらPayPayで支払った証拠画像とその後のネット上の改定された値段とともに上がってきており、いくらで売ろうが本来勝手な小売店側の論理をあまりにも「柔軟に」適用しすぎる嫌いもあるかと思われます。
また、同じような商法としては、AとBを一緒に買ったら○◯万円引きってキャンペーンを打つと瞬間同時にAとBの合計売価が◯◯万円分値上げされた、というような目撃証言もありまして、当然変動する相場とキャンペーンとはそれぞれ独立して運用されているもの、という公式回答を覆す証拠調を行い裁判で訴えようにも時間がかかりすぎることから考えますと、やはり各消費者が賢くなるしかないのかなという感覚を覚えました。
そしてこのPayPay祭りですが、今回は、PayPayの「20%還元セール」という、どう考えてもお祭り騒ぎにすぎないキャンペーンが終了するだけで、本来決済サービスとしてのPayPayとしてはこれから、というところなのに、この祭りに参加した人も傍観していた人も、筆者ですら、まるでPayPayというサービス自体が終了するように感じてしまい、すでにPayPayアプリもキャンペーンでもらったポイントを使い切ったらアンインストールしてしまうくらいの感覚になってしまっているところに、結局みなPayPayだろうが何だろうが、その20%還元という販促イベントだけにしか個人的なメリットを感じておらず、QRコード決済が便利だなどとは特段思っていないところが、すこしさみしいところだと思います。
つまり、誰も得をしていない、家電量販店の人たちも事務作業で大変だったに過ぎず、QRコード決済は特に定着しなかった、ということに落ち着くのではないかと思われます。
何だか、自律する組織や会社になりきれず、やっている事業の社会的必要性のみを喧伝し、地方公共団体や国といった公的機関からの実質的な補助金を得ることがいつしか目的となっている組織と似たような残念な光景が、そこに広がっているように思えました。
つまり、買い時は今だ!
ということなのかもしれません。
そして、支払い方法は早く一つにまとまってもらった方が、売る方も買う方もメリットが出るのは間違いありません。
QRコード決済には慣れませんでしたが、Suica等のFeliCa決済については、あちこちで支払いの実績を積み上げております、レジの手間が嫌いな(でも領収書は貰う)筆者からのコメント記事は以上です。
(2018年12月15日 土曜日)
▷▷次のページは