真田幸村の名声
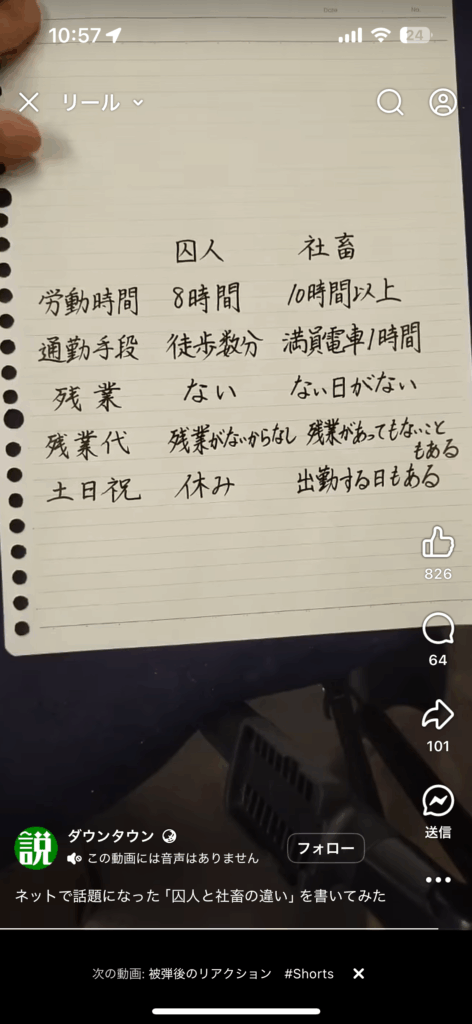
不朽の名将真田幸村公
大阪夏の陣で、正面から攻撃を仕掛けた真田幸村が、後方の徳川本陣に到達し家康は切腹しかけました。幸村はなぜ本陣まで到達できたのですか?幸村さんの名声の理由は何か探ります。
もともと大坂の陣は諸大名にとっては恩賞が全く期待出来ないクソな戦いです。大坂の陣も出陣を拒めばいずれ幕府に潰されるから渋々参戦しただけで戦意は限りなく低いです。幕府クソ絶対。
関ヶ原の戦いからはや10年以上が過ぎて諸大名は徳川家の統治がどんなものか気付いたのも大きい。
古来より御恩と奉公が武家社会のルールでしたが、徳川家はこのルールを奉公か滅亡かの二択に変えてしまった🤮ゲロー
また、関ヶ原前の家康みたいに節約を積み重ねていざという時に備えて軍事費を貯めていても、天下普請を名目に徳川家のために浪費させられる。もちろんこれを拒めば徳川家の強大な軍事力で叩き潰されます🤮ひでえ
しかも冬の陣の後に徳川家は大坂城の惣堀を埋める……という豊臣家との約束を破り、大坂城の総堀を埋めて裸城にしています。最低ー
諸大名の立場で考えるとなんてことしやがるんだ!となるでしょう。太閤秀吉の正統な後継者、右大臣秀頼公。クソじじいの家康なんかより遥かに素晴らしい名君。その貴種に対して三河田舎侍のやることじゃねえだろ、そもそも家康の爺さん、秀吉の部下だったにすぎねー
古来より《囲師は周するなかれ》というのは戦の常識です。相手を必要以上に追い詰めると《窮鼠猫を噛む》となり手痛い反撃を被るからです。
そもそも大坂冬の陣からして言いがかり。鐘の文言にイチャモンつけた田舎もんの浅知恵。ふざけんなよ、ってところです。幕府が豊臣家との約束を勝手に破り追い詰めた結果、豊臣家に残った兵士は戦死を覚悟した死兵だけが残された。死兵になりきれない人の心が残った兵士は敗北がほぼ確定している戦いから逃げ出しています。
恩賞が期待出来ない戦で動かなくまで破壊しないと止めることが不可能なゾンビ兵も同然の死兵と戦わされる……こんなに割に合わない戦も前例が無いです。
タダ働きでこんなのと戦わされるのはやってられないですよ。
諸大名の本音はここまで豊臣家を追い詰めたなら責任をとって徳川家だけで戦えよ! でしょうね😅
しかし、どんなにクソな戦いでも戦意が全く無いとペナルティを受けかねない。それが徳川家のやり方だからです。そのために幕府から自分を守るためには戦意不足と見られないようする必要がある。偽装する必要があるわけです。骨のある奴らはみんな死んでしまった。
そのため、安全な遠距離戦では猛攻撃を仕掛けます。しかし鉄砲隊が中心の編成なので、接近されたら突破を許しています。それを許さないと死兵と白兵戦になるから選択の余地はないのです。
仮に突破を許したところで、家康の本隊以外は襲われる心配がないので実害はない。失うのは自分の名声くらいでしょうか😅大したことはありません。
しかし、それも『真田が凄かった!』と宣伝をすることで最小限に抑えられます。なんで、真田日の本一の侍。これは、かの島津が残した言葉です。
いいなあ…
と本音で思っていた徳川側の声にならない言葉が滲み出る、素晴らしい華向けの言葉じゃありませんか。
牙を抜かれ、這いつくばり徳川の世で生きるのも人生。派手に散るのも人生。だから、大阪は東京が嫌いなわけです。そらそうでしょう。たった400年前のお話。筆者も関西にちょっとありまして、梅田のビックマン前で合コンの待ち合わせなんかをしてましたが、大阪人のこの気質は、連綿と、現代にも伝わっていると感じます。
こうして誰もが白兵戦で豊臣軍を撃滅しようとしなかった結果、最も危険な真田隊の本陣到達を許してしまった……こんなところでしょう。
□□□
大坂の陣の後に幕府は諸藩に鉄砲隊に偏った編成を禁止して長柄槍を重視した編成を命令しています。
鉄砲の割合を見ると小牧・長久手の頃まで戻るでしょうか?
ちゃんと狂った死兵、バーサーカーと白兵戦をやれ! という無体な命令です。
ちなみに、この命令は幕末の第二次長州征伐に敗北するまで続きます。
筆者のご先祖も、信濃國上田、の地の出の地侍、おそらく真田家にしたがって徹底的に徳川家に刃向かって、関ヶ原、大坂の陣と従軍したはずです。
そこで死なずにどこどこまでも落ち延びて、西の最果て肥後國天草までたどり着き、そこで名主として生き残る。素晴らしい落ち延び人生ではありませんか。
どこどこまでも切れない人生というのも良いと思います。真田幸村公も、おそらくお喜びだろうと、わたしは思うのです。
かつて上田城を訪ねることができまして、城門に手をつき祈ることができました。
大阪万博にも、必ず行きたいと思っています。
以上

