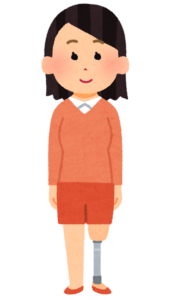日本の雇用慣行では正社員というオプション込みで給料が低く抑えられているという事実
おはようございます。
2018年1月のビルメン王(@shinya_ueda)提供の日本の雇用慣行「正社員」「終身雇用」に関するブログ配信記事です。
日本の雇用慣行においては、新卒(大体において大学学部修了時のことをいう)を毎年4月1日という世界的にはずれた年度初めに一括して採用するという独自のスタイルが取られておりまして、そうして集められた新卒社員に、業界内で定めた一定の給与水準でスタートするという世界的に見れば極めて独特なスタイルが採用されております。
ちなみに、日本の社会構造はここからナイアガラの滝の如く人口減少社会に突入していくわけでありまして、筆者も若いころ「世間」から言われていた「競争社会」「お前の代わりの若い奴などいくらでもいるんだ」的世界観とは全く変わってしまいました。
人は本当にいないので、企業側とすればお願いして来てもらわないといけないわけです。
大きなコストをかけて採用した新卒社員が、例えば3日で辞めてしまった、というようなことは極力避けなければならないのです。
一方パートの時給が上がっていくのは当たり前であり、これは正当な労働力の需給による価格上昇が反映されただけのことです。
企業側としては、毎年一定しか入らない(そしてかなりの部分が途中で離脱する)正社員に頼っていては必要な労働力が集まりませんから、非正規雇用と呼ばれるパート・アルバイト・派遣社員等の時給を上げていきます。
一方で正社員については、時給を上げなくても転職退職あんまり変わりません。
年功序列で給料が上がっていく「権利」がありますので、それを放棄してまで外部に活路を求めるという判断はできないのです。
したがって経営側としては正社員の賃上げのインセンティブはあまりありません。
この点、会社が儲かっている、儲かっていない、ということは「超越」しています。
外部環境が急変している第二次世界大戦(大東亜戦争、太平洋戦争)直前の状況下にあっても、通常の定期異動に定期昇進を行い、飛行機のことなんか基本ほとんどわからなかった司令官を空母機動部隊の司令官とし(航空戦術のわかる人は各空母の艦長クラスにしかいなかった、飛行機というものの時代がそれだけの年月しか経っていなかったため将官級の人材がいなかった)、「先輩に花を持たせよう」とした旧陸海軍を笑えないのであります。
実際、企業の儲かり具合と正社員の給与水準は、会社が赤字の場合は切り詰められますが、会社が儲かっているときはそれほどの相関はないように感じます。
正社員としての、全体の賃上げの低さの原因は、確実に終身雇用年功序列という雇用の身分保障の対価として、高いオプション料を支払って各正社員は「安心」を日々買っているのです。
ですから、会社が大統合したり(メガバンク)、究極的に事業に失敗したり(原発発動機会社や電力会社)した場合においては、正社員たちの狼狽・心配はマックスに達します。
いずれも、オプション料を支払っていた終身雇用年功序列という保障が取れるという恐怖心からくるものです。
安くない機会利益を会社という運命共同体に日々支払っているわけですから、その落胆や失望、会社に対する怒りもわかります。
筆者もメガバンクの構成要素の一つであった銀行に勤めていたこともありますので、その気持ちは痛いほどよくわかります。
さて、このような状況であれば、そのぬるま湯状況から飛び出し、外資系および日本的雇用慣行のない会社に転職すれば給料は上がるでしょうが、身分保障は失います。
したがいまして、身分保障による幸せ増幅機能がどの程度個々人の正社員にとって有用かという観点からすれば、それもポジティブに考えれば納得感もあるかもしれません。
極端な話をしますと、例えば東大東工大工学博士の天才プログラマーであっても、日本の、例えば白物家電メーカーの代表格のこの木なんの木気になる木のグループに就職したとすれば、事務職社員と同じ年収400万円からスタートするというのが、現在の日本の平等な雇用慣行であります。
むろん、この天才プログラマーが適正な処遇を求めていくことはできますが、そのスピードは、年功序列終身雇用オプションを支払っている以上非常に小さいものに留まることが予想されます。
同じ条件であれば、たとえば機電情報系の博士に加えて、プログラミング、英語、中国語をそうですね1年くらいかけてとりあえずできるレベルまでマスターしたら、中国の深圳市(Shenzhen)で年収1,000万円、アメリカのシリコンバレーで年収2,000万円の初任給の待遇になる人材だと思われますので、その格差たるや驚きです。
世界は広い、そういったお話でした。
とりあえず大きな話をしたので今日は奮発してお昼は1,000円のラーメンチャーハン定食を食べようと決意した日本のサラリーマン筆者からは以上です。
(平成30年1月26日 金曜日)
▷▷次のページは