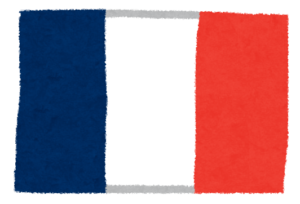一票の格差軽減のための衆議院選挙区の区割り変更案が答申されました
おはようございます。
2017年4月の政治制度に関する配信記事です。
2017年4月、どんどん日が長くそして暑くなってきておりますがみなさんいかがお過ごしでしょうか。
さて今回は選挙は統治機構の根幹であり選挙マニアを自任しております筆者より、ついに総務省より提示された衆議院議員選挙のための選挙区の区割り変更案についてです。
今回は、2015年に実施された国政選挙の結果のみならず、そこから5年後の、現時点では将来時点であるところの2020年(2回目の東京オリンピックの年です)における将来人口予測を踏まえて、いわゆる一票の格差が2倍以内に収まるように、各都道府県の市町村のさらに町まで細かく調整するという、非常に難度の高い技を駆使しまして、格差を1対1.999倍まで「縮小」することに成功しました。
現行の選挙区区割り制度をできるだけ変えたくない現在の国会議員(衆議院議員)と選挙管理を担う総務省により、法律で要求している2倍以内をギリギリ達成した今回の案ですが、それでも選挙区を減らされた県などからは批判が起こることになっております。
今回の区割りによって選挙区数が減らされた県
たとえば岩手県は3区に減って一つの選挙区が四国並みに広くなってます。
九州でも熊本県と鹿児島県は選挙区が一つずつ減りました。
ちなみに日本地図をご覧になればわかるのですが、岩手県は四国4県の広さに匹敵すると言われていますが、今回統合された岩手県新第2区はなんと岩手県の半分以上が一つの選挙区となるというわけです。
1票の格差という考え方ですが、これではますます広い県土にその地域性をわかった国会議員は減る一方ということになる、というのが田舎側からの批判です。
人口が少ないから国会議員も減らせば良い。
各選挙区の有権者の数を均等にすれば良い。
職業選択及び移転の自由を憲法は人権として保障しておりますが、これでは地方は衰退するばかりです。
人口が減っても県土の面積は当然にそのままであり、そうした打ち捨てられた県土を減らして有効活用していきましょう、というのが政治の大切な機能の一つであるという主張です。
人口比例ですから、126万人いる岩手県には衆議院選挙区は3つ、一方1,363万人いる東京は25の選挙区があります。
ちなみに最も有権者数が少ないと見られる鳥取県は、人口57万人で2選挙区です。
1県1選挙区という県はまだないですが、いよいよ鳥取県の人口減少が待った無しとなり、早晩1県1選挙区という県も現れると見ています。
先回りで将来の望ましい人口配置に沿った区割りとするという解決策
筆者は、東京に25の選挙区から選出されるそれほどの数の国会議員が本当に必要かという議論は一旦横に置き、より将来の好ましい国民の人口分布に即した区割りにするという案ではどうかという考えを持っております。
すなわち、過疎の地方を担う国民の移住なり再配置を促すために、地方の選挙区を厚く配分するというものです。
同じような事例は、甲子園を目指す高校球児の分布にもよく表れています。
野球が盛んで野球少年を多く輩出する関西圏の中学生たちは、まずは(2017年現時点では)大阪桐蔭や履正社といった超一流高校への進学を目指します(昭和時代ならば間違いなくPL学園でしたでしょうが)。
そこに入り腕に覚えがあれば、レビュラーとなり甲子園出場の可能性が非常に高まるからです。
そのセレクションに漏れた人間は、次に大阪を出て全国の強豪校に集まります。
例えば最近力をつけてきた熊本の秀岳館という高校は、そのレギュラーの出身地が大阪ばかりです。
大阪弁を喋る高校球児が肥後くまもと郷土の代表か、という問題意識は棚上げいたしまして、このように、高校野球に出場するという目的のため、人は民族移動を行います。
そして、中学時点では2軍だった彼ら都落ち組が、リターンマッチで甲子園で合間見え、そして勝利するといったこともままあるわけです。
これは、立派な中央から地方への人の流れであり、衆議院議員選挙区の区割りについても、このような技を駆使すれば、増員された選挙区において、地方に中央からの落下傘候補と地元弁士との壮絶な選挙戦といった手に汗握る場面と健全な競争が起こるかもしれません。
良い意味でも悪い意味でも、小選挙区での地方選挙区での勝利は十中八九保守系で決まってしまうという側面があるところ、こうして将来の人口増加を「期待」した人員配置を行うことで、むしろ現時点においての1票の差を認容するという政策もあるかもしれないのです。
本当に1票の格差というものが何よりも問題であれば、全国を1選挙区として、全国で選挙活動を行い、1位から400位くらいまでを順に当選させれば良いのです。
これですと、全国で1選挙区ですから格差の出ようがありません。
みんな、1票は等しく1票です。
しかし、これでは全国的に名前だけが知られたタレントばかりが得票を伸ばすことは間違いないでしょう。
ますます地方の実情というものは国会に届きにくくなります。
いろいろ考えておりますと筆が止まらなくなりますので今回はこのくらいといたします。
永遠の新人候補の筆者からは以上です。
(平成29年4月23日 日曜日)