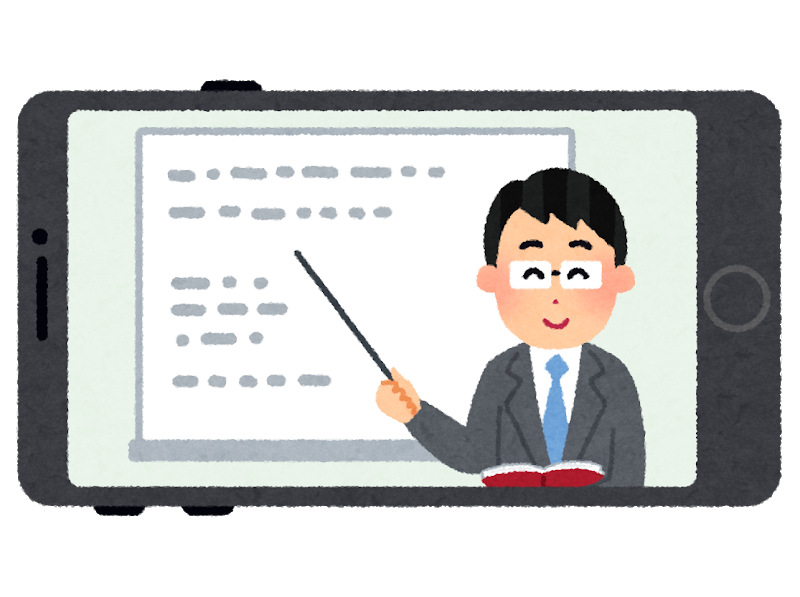才能と教育というものに対する最も効果的な態度や振る舞いについて私見を述べておきます
おはようございます。
教育というものについて語る、ビルメン王からの2019年1月の配信記事です。
教育というものについて書いてみます。
自分がどのように教育されたかということを少し振り返りながら書き始めます。
スポーツに限らず、芸能でも囲碁や将棋のようなパフォーマンスにおいても、勉学や研究においても、それらの個々人の振る舞うパフォーマンスは、当然遺伝的要因がありますが、どのような才能の原石を持っていても、親や周囲の環境によってはそれがうまく伸びない、もしくは才能があることすら看過される場合が多いと思います。
そして、自身にどのような才能があるかということは、自分自身が実はよくわかっていて、外部にそれを出すことを厭わない自信家の者と、できるだけ出さないようにしている臆病者の者がいたとしても、自分の才能のありかについては、結構正確に認識していることが多いと思います。
例えば、スポーツにおいても勉学成績においても、「あいつには勝てない」と思うものは感覚的にいるものですし、「あいつには負けないな」というのも結構正確にわかるものです。
ここで大切なのは、この「感覚」は瞬間瞬間のものにすぎず、一ヶ月もすれば子供の世界であるとなおさら、容易に変動しうるということです。
ですので、最も才能を伸ばす方法は、ある一定期間、じっくりと、その競技なりスポーツに、淡々と、負荷をかけすぎず、習慣として間を置いて取り組み続けるということでしょう。
スプリントでの足が速いとか持久力がある、といった「才能」についてはかなり人生の初期段階からわかるものですが、例えばテニスやゴルフ、スキー、卓球、囲碁や将棋や絵描きや漫画家といった「技量」を要するような競技については、一定以上の「習慣」「慣れ」が決定的に重要です。
囲碁や将棋にしても、その才能があるかどうかは、しばらくその競技に没頭する時間がないと難しいわけです。
であることから、こうした世界で一人で生きていくには、自分で考えて自分で動くということが徹底的に重要になってきます。
技術面を教えたりトーナメントに出場したりする段取りは、プロのコーチや専門家に任せ、親や周囲の人間は、その才能に目覚めた人間に対しては、あまりごちゃごちゃうるさく言わない方が当人の才能は発揮されるようです。
自身の才能に目覚め、その才能によって飯を食っていこうと覚悟した人間は、いくら年が若かろうが立派な大人です。
であるからして、その才能について特段の知見を持たない親や周囲が、その才能に関して論評することを当人は全く求めていませんし、何かアドバイスをしたところで余計なお世話とばかり聞く耳を持たないでしょう。
しかしながら、その才能についての特段の知見を持たなくても、「人間」としてどのように振る舞うべきかということを教えることはできます。
で、そのことの方が決定的に重要です。
受験生だから、朝は起こしてもらいご飯を作ってもらって布団を上げてもらう、というのでは、現役で東大に合格したところで、その後の人生において学習を続けていく、ことは難しいかもしれません。
親や周囲への感謝の気持ちがどこかで芽生える、ことがなければその後の成長は厳しいでしょう。
高校野球で甲子園を目指すため、野球の腕に覚えのある者は野球留学して全国の高校野球強豪高の門を叩きます。
その頂点の一角に君臨する、大阪桐蔭高校での野球部の寮生活は、自主性の塊だそうです。
そして、高校一年生で入寮してわずか1ヶ月、ゴールデンウィークの頃には、新入部員たちの顔つきは精悍になり、それと同時に親や周囲への感謝の気持ちをノートに綴るそうです。
自分の才能を伸ばすための環境整備に、いかに多くの人たちの陰ながらの献身があるか、そういうことを身をもって知った人間は強いと思うわけです。
これは、大事なことを決める時には必ず一人で決めるという自立心を養うことにもつながります。
人と違う人生はそれなりにしんどく、そして誰のせいにもできないわけです。
自立心が強いということは、癖も強くなるかもしれませんが、起こったことの責任を他のせいにしないという強さにもつながるわけです。
指図するのもされるのも嫌がる性格になり、周りで起こることに対して一定の距離を置くようになり、淡々とした感じになり、感情の起伏が少なくなります。
しかし、それは、感情が乏しくなったわけではなく、大人になり芯の強さが備わった、ということでもあるのです。
自分の人生の意思決定プロセスに、いつまでも親や周囲の影がついてまわることの障害は、結構大きく、例えば、なぜ勉強するのかという根本的な疑問に自分なりの回答をつけられないまま、中高一貫の受験対策学校を卒業してしまい、受験はくぐり抜け大学に入学したものの、カリキュラムを指導してくれる人がいないので困ってしまった、という人も知っています。
大学入ったから思い切り好きなことができるね、という「一般的な」感覚とは真逆で、新しい一本道のレースを求めないと安心しないわけです。
小学校の高学年から、すでに塾漬けで、中学受験して、いつも席次とテストの成績がついてまわれば、そうなるのも仕方ない面もあるでしょう。
しかしながら、どこかで、自分のやることは自分で納得して折り合いをつけなければなりません。
そして、これは、子供の人生に過度に容喙する親に共通の問題点であるように思います。
親にも親の人生があり、特に才能ある子供につく親は、当の子供以上に子供の人生にこだわる嫌いがあるようです。
しかしながら、親子で周りが見えなくなるぐらいはまり込み、子供の練習量や学習量ばかり増え続け、大人顔負けで勝負に賭けるようになってしまうのは本当に不幸です。
高校野球で4,000校の頂点に立つ、つまりこれは一高校あたりの野球部員の平均を25人とすれば、10万人の野球部員の頂点に、レギュラーの10人(野手8人と投手2人)が立つ、すなわち一万分の1、0.01%の確率であるということですが、そんな瞬間に立ち会える勝者はほんのわずかです。
ちなみに、2019年1月の大学入試センター試験を受験したのが50万人、東大の定員が3,000人ですから、東大に入る確率は千分の6、すなわち0.6%ですから、上の甲子園優勝ナインに入ることよりはるかに簡単であるということになります。
スポーツや芸能の世界の方が、はるかに厳しいのです。
そんな、宝くじのような勝負の世界の結果ばかりにこだわる状態が数年続くと、大体子供は心身ともにすり減ってしまい、その競技自体が嫌いになってしまいます。
筆者が、40歳を大きくすぎても楽しく野球やサッカーができるのは、それほどの野球の才能もサッカーの才能もないとはいえ、それでも野球は子供会ソフトボールのキャプテンであったくらいにはボールも投げることができて足も速かった、リフティングはできないけれども泥臭くサッカーボールを追うくらいの振る舞いはできたのでDFとして出場するくらいはできた、という「程度」の才能であったことが実は幸いなのです。
筆者よりはるかに才能もあり努力もしてきた野球人やサッカー人が、40歳をすぎると壊れたり精神的に擦り切れそれほどのやる気もなくなってしまっているように見え、実際のパフォーマンスも落ちてきているのを見るにつけ、人間万事塞翁が馬であり、たとえプロ野球選手であった人にも、70歳過ぎれば勝てる要素もできるのではないかと思っているのです。
もちろん、65歳をすぎても130キロを超える直球を投げる元ロッテの村田投手のような、超人的な方もおられますが、このように、才能を磨いてそれで飯を食っていく、ということを決める決断は自分自身にしかできない、ということは繰り返し言っておきたいと思います。
最後に、子供の将来に容喙しすぎる親に対して。
筆者なりの意見は、子供が何らかの才能を持っているとわかった時点で、一番いい親の態度は、ひっそりそれを認めて喜び、あとは自分の人生に集中することだと思います。
目標を持てとか、勝てとか言っている親自身に、実はさしたる目標がないこととを、子供はちゃんとわかっていて、冷徹に察知してしまいます。
勝負しろ、負けるなと言っている親が、実は一番勝負していない、という寒い状況にならないように、自分の戦い、自らの人生にきっちり向き合うことから始め、己に恥じぬ人生を生きた方が、そうした態度で背中で語る方が、ずっと子供の「観察」に耐えうるのではないかと思うわけです。
であるからして、一番の「教育」は、自分がこのようにしたいという姿を、自分自身の人生で背中で見せて実践していくというのが、最もふさわしい親としての振る舞いだと思っています。
自分の子供がドラフトにかかるか、を心配してばかりの親より、今年のドラフトには自分がかかりたい、そのためのトレーニングを積んでいる親の方が何か話が盛り上がるような気がしています。
結局、
・子供だろうが大人だろうが個人として尊重してやる気を削がないようにする
・やる気を削がないように、大抵のことについては淡々として一喜一憂しない
ということかなと思います。
またとない才能に触れると、いろいろいじってみたくなるのは人情ですが、他人ではなく自らの中に、そうした才能のかけらを探すほうが面白いと思います。
ブログ記事が世界中で読まれて、文壇デビューするかもしれないと思うと楽しくて仕方のない筆者からの記事は以上です。
(2019年1月26日 土曜日)
▷▷次の記事は