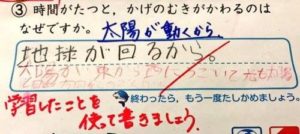(2018/12/27)ウイルスがなぜ宿主を殺してしまう場合があるかその答えはレゼルボアが知っているという話です
おはようございます。
2018年12月のウイルスに関するビルメン王提供のブログ配信記事です。
本日は、人間にとって怖い病原体やウイルスについて専門的なことをわかりやすく解きほぐして話してみる記事を書いてみたいと思います。
医師免許や獣医師免許、歯科医師免許や薬剤師免許、看護師免許などを持っている人ならばご存知なのでしょうが、筆者始めその手の素人には実のところよくわかっていないので、あえてここに記しておくものです。
人を死に至らしめる病気を運ぶウイルスは、その宿主の身体を食い尽くし、そして命を奪えば自らも死に至るのは自明なのに、どうして、そんな大切な宿主を死に至らしめるまで攻撃しつづけるのでしょうか。
これは思えばおかしな話で、例えば、時は江戸時代、神尾春央(かんおはるひで、貞享4年(1687年) - 宝暦3年5月5日(1753年6月6日))という徳川幕府の旗本侍(官位は若狭守)がおりまして、これは年貢を非常に厳しく取り立てた酷吏としてつとに有名で、彼の言葉として「胡麻の油と百姓は絞れば絞るほど出るものなり」と述べたとされる有名な話があるくらいですが、それでも、「百姓など殺してしまえ」とは書いておらず、搾り取るだけ絞りとるが、生かさず殺さず、という姿勢を徹底しているという点で、この現代も人間を悩ますウイルスとは一線を画しているのであります。
ウイルスも旗本も、それ自体単体で生産活動に従事しているものではなく、ゆえにそれ単体では生きられず、なんらかの細胞もしくは農民に寄生して暮らしていく必要があるわけです。
もちろん、厳しく年貢を取り立てた旗本に比べて、ウイルスの方は非常に簡単な構造をしておりまして、ゴマの種のような硬いタンパク質の「殻」のなかに遺伝情報が詰まった「核酸」がそのまんま入っているだけ、というような極めて簡単なつくりになっています。
そして、核酸に入っているタンパク質の遺伝情報は、材料さえあれば勝手にコピーして増えていくようになっていて、その遺伝情報に従ったウイルス(生命とも言いがたいですが原始的な生命と言えます)が新しくできて、結果としてウイルスが増えていく、という現象が起こります。
従って、ウイルス自体はその近くに養分があれば、勝手に遺伝情報を晒して自己増殖するだけの、いわば機械に過ぎませんので、彼らが自己増殖しようと「思って」やっているわけではありません。
たまたま、ウイルスが入った宿主の細胞の中で、コピーできる限りコピーする、というだけですので、材料となる細胞が死ぬなりして増える材料がなくなれば、そのまま増殖が止まる、というだけのことなのです。
ウイルスは侵入に成功した細胞を持つ宿主の生命体自体を別に「殺そう」などとは思っていません。
しかしながら、そういう物理現象の結果、宿主が結果的に死ぬことはよくありますが、別段そこに特段の強い因果関係とか恨みとか思いとか経営理念などがあるわけではないのです。
なぜかといえば、それはウイルスが細胞を「殺さずに」増えることができる場合がよくあるからです。
例えば日本脳炎ウイルスがヒトに感染すると場合によっては重篤化して死に至る場合もあります。
恐ろしい病気です。
人間にとっては、です。
しかしながら、このウイルスは、ブタの細胞では増えても細胞に悪影響が特段出ないのです。
しかしながら、ブタの体内で増えたウイルスが蚊を媒介してヒトやその他の動物に感染したとして、その「宿主」がたとえ死んでいなくなったとしても、相変わらずブタというウイルスが増える場所は確保されているのです。
ウイルスとしては、単に有限の宿主であった、というだけであまり代わりがないのです。
それに、永久に生きる宿主や生命というのがない、ということもこのことの答えになるかもしれません。
ウイルスによる病気で死のうが、ウイルスは直接の影響を下さないがどっちみち時間の経過で寿命で死ぬか、その違いは少なくともウイルス側にとっては特に関係ない、ということになりそうです。
この場合の、ブタは日本脳炎ウイルスにとっての「レゼルボア」と呼ばれます。
ヒトを含むウイルス感染によって悪影響が生じる動物は「感受性動物」と言われます。
つまりウイルス増殖によって感受性動物が死のうが死ぬまいが、ウイルスにとっては根拠となる、増殖可能な場所(寿命まで宿主でいてくれる)、「レゼルボア」というユートピアが有る限りにおいて、そんなことはどうでもいい話なのです。
レゼルボアがある限りどうでもよく、攻撃しすぎる(増えすぎてその細胞での増殖の機会を失う)ということにもならない、ということです。
今日はブタにとっては無害ですが、人間にとっては有害となる日本脳炎ウイルスを例に、ウイルスというものの本質に迫ってみました。
理科や生物は割と得意でしたが、保健体育についてはあまり得意ではなかった筆者からの記事は以上です。
(2018年12月27日 木曜日)
▷▷次のページは