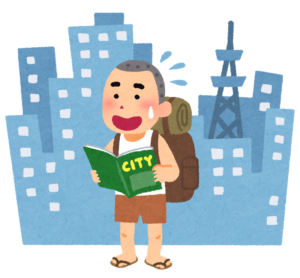やらない理由を探すより解決すべき課題と捉え取りくむ方が面白いはず
おはようございます。
2017年4月の気合い入った放談の配信記事です。
慎重で準備を重ねることは大切ですが、それは近く本番に臨むという前提あってのことです。
迅速に動いて、たくさんのことをするというのが組織や個人において大切です。
準備や慎重さは、迅速に動くためのふるまいや態度であるべきで、それ自体が目的化されてはいけません。
つまり、迅速に動くということは多くの失敗も内包しています。
しかしながら、慎重で何もしないというのは、全く進歩しないことのみならず、貴重な機会を失いつづけるという意味で罪悪ですらあります。
成功の反対は、失敗ではありません。
やったことの結果が返ってきて、好ましいものを成功、好ましくないものを失敗といいますが、それは主観的に決定されることでしてやったことの結果がわかるという意味では同値なのです。
つまり、失敗ではなく、(主観的に)うまくいかなかったことがわかったというのが評価としては正しいわけです。
そして、試行錯誤で繰り返されなければ、行動を起こした結果起きるべき事象を「成功」と認定できる機会も限られることになります。
ある一定の割合で成功が紛れていることがありますが、この確率をあげようと事前の準備や調査、練習ばかりに没頭して本番の肝心の行動に移さないということが日本社会ではよく起こります。
水に入らないと泳ぎ方はわからないのに、クロールや平泳ぎの形を陸上でなぞりつづける、といった間違ったアプローチがそこかしこで見られます。
イチロー選手になってから打席に立とうとしても無理です。
イチロー選手はまず打席に立って三振や凡打をより多く経験したからこそ、あれだけの安打数の金字塔を打ち立てたわけです。
失敗と成功は表裏一体なのです。
4,000本ヒットを打つということは、8,000打席は凡打かフォアボールであったわけで、その失敗の多さたるやそのレベルも常人には及びもつきません。
まずやりたいことを明確にする、そしてやってみようと考えてトライする。
その結果、うまくいくこともあればそうでないこともあります。
しかし、うまくいく場合もうまくいかない場合も等しく経験として人は成長します。
やらない理由探しは虚しい
このときに、やらない理由や言い訳を考えてやらない場合、やらないことの正当化のため、いくらでも言い訳を考え付きます。
時にはやっている人の足を引っ張るような真似もしてしまいます。
やらないくせに、やらないことの言い訳で弁が立つということにならないようにしたいと思います。
そして、できない理由を教えてくれる人は完全に、100%できないので、教えられた方も間違いなくできない人になれます。
できない理由には近寄らないことです。
人間、少しばかり長い時間、例えばそうですね、150年くらい経てば皆長期的にはきれいさっぱり死んでいるのですから、できないことを考えるのは損でもあります。
何もしない理由を探していろいろ考えるというのは、よく考えれば矛盾しています。
やらないのですから、考える必要もないわけです。
成功の反対は、何もしないことであるということは昔からいろいろの人から言われてきました。
例えば、最上は行って成功すること、次善は行って失敗すること、普通なのは行わず黙っていること、最悪は行わず他者の批判ばかりすること、というような感じです。
本番あっての練習
日本人は丁寧できちんとしているので、店を開いたり起業したりする時に完璧に準備した「気」にならないと実行に移さない人が多いのかもしれません。