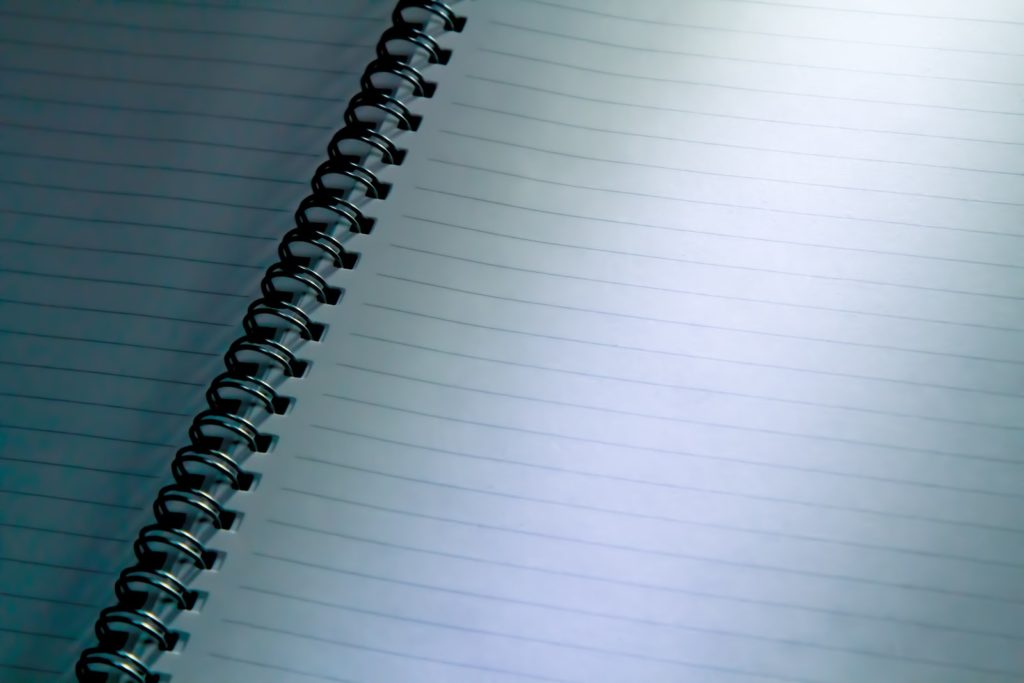(金融用語の基礎知識)「銀行」と「投資銀行」の違いを簡単に述べる
おはようございます。
2017年3月の銀行に関する配信記事です。
普段何気なく使っている銀行という言葉ですが、ここでは紙面を借りまして、消費者金融業界や投資銀行業界と合わせて少し講釈させていただきます。
銀行という預金金融機関と証券会社を代表とする投資銀行との違いをここで改めて確認しておきたいと思います。
銀行、とは各国当局の銀行法に規定され規制がかけられている通り、基本的に預金者の預金を保護するために、余計なことをさせないという金融当局の監視のもと、いたいけな消費者や国民から預金という形での資金融通を特権的に受けることができるものを言います。
特権的というのは普通企業が資金調達をする場合、銀行から融資証書や手形をもって借りるか、株券や債券、の形で発行市場に証券会社を通じて証券発行をしなければならないところ、いつでもどこでも「預金証書」である通帳に一行足すだけで、預金者のお金を「預かる」ことができるという点です。
消費寄託契約といいます。
預金者が銀行にお金を「預けた」と思うことは信用の証
消費者のほうも、銀行に金を貸した、とは思っていません。
国家による預金保険機構というセーフティネットから、どんな銀行も潰れても一人1,000万円までの預金は保護されます、というお墨付きですから、そうそう銀行に対する信頼は揺らがない、ということになります。
しかし証券会社は違います。
いくら預金的な運用をしていても、元本の保証はありません。
あくまで投資銀行はノンバンク、預金を受け入れることはできず、あくまでそうした主体に何らかの金をつけるということは「投融資する」ということになりますのでいつでも返して引き出すことができるわけではありません。
この点、お忘れなきように願います。
逆にいいますと、かように国の金融システムに守られている銀行の預金者に対する責任として、銀行員はそれはそれは固く資産査定して普段からストレスのたまる仕事をさせられているとも言えるのです。
ダイナミックな運用をしたいのであれば、銀行よりも証券会社(投資銀行)と付き合って話を聞いた方が随分早い、とお感じなのであれば、かような金融業上の違いが金融機関の取引態様を決定づけているということがわかるかと思います。
昔銀行員、コンサル会社を経て今は不動産屋の筆者からは以上です。
(平成29年3月6日 月曜日)
▷▷次のページは