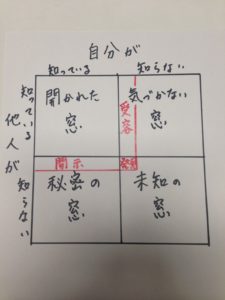日本が貿易収支赤字国に転換してから数年経ちました(2014年経済の話)
 |
| 海外貿易 |
おはようございます。
2014年1月末の配信記事です。
日本が貿易収支赤字国となってから、2年が経ちました。1年前の衆院総選挙で誕生した第二次安倍内閣が主導した金融緩和・財政出動政策(いわゆるアベノミクス)により、ここ1年で以下のような流れが現出しました。
まず、大幅な金融緩和で日本通貨「円」の価値が下落しました。
要するに円安になりますが、これだけでは実体経済には関係ありません。
次に円安の恩恵を受けるであろう輸出関連企業の生産量や(海外)販売額が増えます。
ここではじめて実体経済にプラスの効果が出ることになります(諸外国からは自国の製品が売れずにやっかまれますが)。
そして、その効果は国内の消費拡大にもつながり、内需拡大によるデフレ脱却への力強い足音になるであろう、というわけです。
東日本震災後の貿易収支は赤字基調
しかし、皆さんご覧のように、東日本大震災前までずっと続いていた日本の貿易収支が赤字となってしまいました。
震災以降、エネルギー関連輸入が大幅に増え、そして円安効果によりさらに輸入「額」が増加した結果、その輸入増加が輸出増加効果を軽く打ち消し、全体では大幅な貿易赤字となったのです。月に1兆円、年間12兆円という大きな赤字という状態です。
更に言いますと、燃料代を払っているのは所得階層にかかわらず全国民であり、輸出関連企業は企業や個人事業の一部ですから、この為替の変動は全所得者から輸出関連企業への所得移転効果しか生んでいないとも極論されるのです。
もちろん、貿易はモノの売買だけではなく、金融取引や投資関連の所得収支も合わせて総合的に見なければなりませんが、貿易収支に関しては赤字が常態化しているという事実は認識しておく必要があります。
輸入輸出は表裏一体であり、単純に円安で輸出が良くなって、景気もよくなっているといった理解明快ストーリーではないということです。
経済教室からは以上です。
(平成26年1月29日)