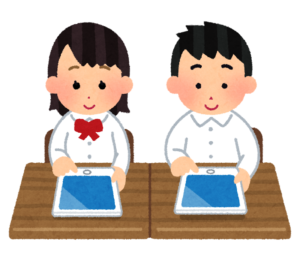クラウドシステムを用いた学習ノウハウの共有化についての論考です
おはようございます。
2018年4月の英語学習に関する配信記事です。
直近に受けたTOEICのスコアが気になる筆者です。
スコアの前に、やっぱり実力をつけるのにはどのようにしたら良いか、自分なりの隙間勉強法を今回は記載して、広く皆さんの助言なりをいただこうと思います。
まず、筆者は日本の受験勉強スタイルで育ちましたので、リーディングのやり方はあまり困りません。
とにかく英字新聞だろうが穴埋め問題だろうが、多くの英文に触れて読みこむ、これで十分だと思っています。
確かにリーディングについても一部、文法的な言い回しやコロケーション(日本語でもありますけど、目薬を差す、といったり辞書を引く、といった決まった言い方)といったところで若干の考慮が必要な部分はあるけれども、特に方法論で困ることはなくて、あとは英文読むのをやるだけだと思っています。
しかしながら、リスニングはそうは行きません。
英語圏にぶち込まれて日本語は遠い国にワープできればいいのですが、なかなか日常的に英語を耳にするという環境に身を置ける人間は、実は今の日本でも少ないのではないかと思っています。
こうした英語独学話者にとって、リスニング力をどう強化したら良いか、ここはとても課題になってきます。
真面目な学習者ほど、迷路のように解決策が見つからないわけです。
ここで、少し語学を勉強と思わずに、所詮コミュニケーションの一手段に過ぎないと考えることができれば、インターネットなどを介した英語の生の声や音源を探し当て、とにかく聴きまくるという環境を自ら構築することができると思います。
筆者も、リスニングの講座を、それこそNHK基礎英語から一通り取り揃え、時間があれば聞き流すということを始めた結果、累計で、感覚的に500時間くらい聞いてきたところで、なんとなく英語というものがわかるようになってきて、それからはとりあえず聞いてわかるところを拾うという感じになってきました。
おそらく、TOEICのリスニングで満点を取れるレベルに達するには、あと500時間、合計1,000時間程度は最低限必要ではないかと個人的な感覚で思います。
とすれば、とにかく英語のラジオでもNHKニュースでも、聴けるものはなんでも聞いておくというのが良さそうです。
今は、スマホのポッドキャストで無料の英語のニュースやショートストーリーも聞けますし、アマゾンプライムで無料の映画(字幕なしですが)も観ることができます。
こうしたクラウドシステムによるノウハウ共有が今日の教育現場に与える影響はものすごく大きいのですが、残念ながら現在の教育システムは江戸時代の寺子屋時代以降の(それはそれでとても優れたシステムですが)座学スクール形式を踏襲していて、個人個人の興味や深度に即したものになっておりません。
このあたり、もう少し体系的に理論立てて突き詰めてみたいと思います。
実験ソースは自分自身ですので、適宜進捗ありましたらレポートいたします。
こちらからの、「勉強のやり方」についての記事はこのようになりますがが、勉強への興味の持ち方については相変わらずわかっていない筆者からは以上です。
(平成30年4月21日 土曜日)