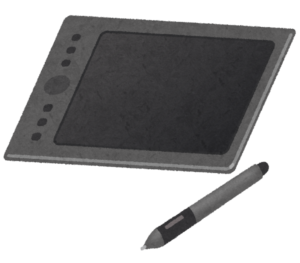インフレターゲット政策は少子高齢化人口減少に阻まれ未達に終わるか
おはようございます。
2017年2月の配信記事です。
日銀総裁が黒田総裁に替わって、インフレターゲットという物価上昇を日銀の目標とするという政策が取られて早数年が経過しようとしています。
デフレを脱却するために、インフレ率を政策的に設定して、政府と中央銀行がそれに向かってマーケットに対して期限を定めない金融緩和政策、すなわちベースマネー(市中通貨)を供給し続けるのが今世界中の先進国で行われているインフレターゲット政策と言えます。
市中に出回る実質通貨の絶対値が多くなれば、需要と供給の関係で必ず物価は上がるというのは経済の初歩という経済学者の主張もあります。
しかし、通貨「量」だけの水準だけで各国比較するとというのは少々危険かと思われます。
例えば日本ではモノやサービスを買うときに現金で支払うのが一般的ですが、米国などはクレジットカードや小切手で支払うことが一般的です。
最近では日本においても電子マネーやクレジットカードが主流となってきましたが、まだまだ「いつもにこにこ現金払い」の国です。つまり、日本は市中に出回る通貨・現金の量がもともと米国などより圧倒的に多いのです。
諸外国の紙幣に比べ、日本の紙幣や硬貨が遥かに高品質で偽造しにくいというところも一役買っていると思います。
そのような中にあって、すでに市中に沢山の通貨が供給されているので、インフレターゲットが目指す政策対応はすでに行っている、むしろ通貨の番人たる中央銀行がそのような「インフレ政策」に手を貸せば、通貨に対する信用が失われて取り返しのつかないことになるというのが2013年初までの日本銀行の態度でした。
そんな中、特にリーマンショック後、米国も欧州も大幅な金融緩和を続行してきましたが、現金社会である日本の中央銀行の金融拡張の度合い(通貨の増加割合)は、実際とても少なかったのです。
各国のベースマネーの絶対量を比較するのではなく、変化量を比較しないと、金融緩和が十分か否かを論じることはできません。
2013年になり政策変更が行われ、日銀のベースマネーは2年で2倍にするということになりました。
こうなると既に市中にもともと現金決済でたくさん流通している貨幣ですが、最近現金がだぶついているなあという風潮になってきており名目的なインフレも各種指標から少しずつ出てきたように思います。
しかし、実体経済の回復が確認を見極め、その瞬間にこの大規模金融緩和の「終了」を宣言しないと壊れた蛇口から水が出続けるようなことになり、日本円は坂道を転がるように信認を失ってしまいます。
そのタイミングを図る「勘」が金融政策当局に働くことを期待しています。
物事は何よりも撤退が難しいものです。
インフレターゲット論は博打に近い?
インフレターゲット論は、大御所の経済学者や実務界のエコノミストの中には効果がないと評判が悪い部分もあります。
その論拠としてケインズが言った「流動性の罠」という現象があります。
いくら市中に出回るお金の量を増やしても、皆がお金を貯め込んで投資をしない状況です。
背景にあるのは、金利が低いから何に投資しても現金を持っているのと利回りは変わらないし、むしろ金利が上がったら債券の価格や不動産価格が値崩れして損をするのではないかという不安です。
すなわちゼロ金利の下でお金を増やしても、経済を活性化する効果はないというのです。
しかし、上記の論調の人たちは、債券市場だけ見ていて、株式市場や不動産市場、賃料動向などまで広く経済を見ていない、という反論もあります。
株式や不動産への投資機運の高まり自体が株価を上昇させ、その結果企業がより投資しやすくなるということがあるのではないかと期待したいのです。
金融緩和で担保となる不動産価格が上がると、お金が借り易くなり、そして多少のリスクを伴っても新しい投資を行ない利益を増やそうと考える人が増える。
これがインフレターゲット論の主張です。
経済も感覚が支配する時代に入ったのかもしれません。
感覚で投資するといつも間違う筆者からは以上です。
(平成29年2月4日 土曜日)