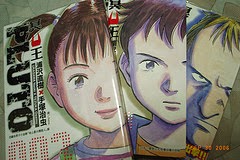ICカード普及によるJR私鉄乗車に関して二つの運賃が発生したことの話
 |
| Suica |
おはようございます。
2015年2月の配信記事です。
花の都大東京にお住まいの皆さんには遅れたニュースになりますので、ニューとも言えませんが、筆者が東京出張して驚いたことを記しておきたいと思います。
地下鉄JR私鉄交通網が非常に発達している大都会東京におきまして、当然移動手段は「交通系ICカード」なのですが、消費税8%への増税のタイミングで、首都圏のJRと私鉄、そして地下鉄がIC乗車券の1円刻みの運賃を初めて導入したのです。
1円刻みの運賃は10円刻みに比べ、増税分をより細かく運賃に反映できるわけですが、通常の発券切符において1円単位の販売とすると、大量の一円玉を処理することが必要となり、そもそも1円玉対応していない券売機にその対応を迫るのは困難、さすればより実態を反映すべき1円刻みの運賃をIC利用者に先行して開放しようという「試み」と公式には説明されるようです。
実際にどのくらい運賃が変わるのか
例えば、現行150円の東京-上野間は、IC乗車券が154円、切符購入では160円となります。営団地下鉄の初乗り料金、こちらもICでは165円ですが、切符だと170円です。
利用者としてはあまり意識しませんが、券売機で切符を「発券」し、それを自動改札機で「処理」し「回収」するコストを考えるならば、電子マネー化による二重価格(IC運賃のほうが概ね安い)も大した混乱もなく許容されているような気がしました。
しかし、企業や公務における「旅費精算」においては、ICか切符かどちらでの利用かを明示して行わなければならず面倒になります。
何事も、よい面難しい面があるものです。
IC化は便利ですが、残高が残っているEDYカードを、誤ってそのまま捨ててしまったことのあります残念な筆者からは以上です。
(平成27年2月21日 土曜日)