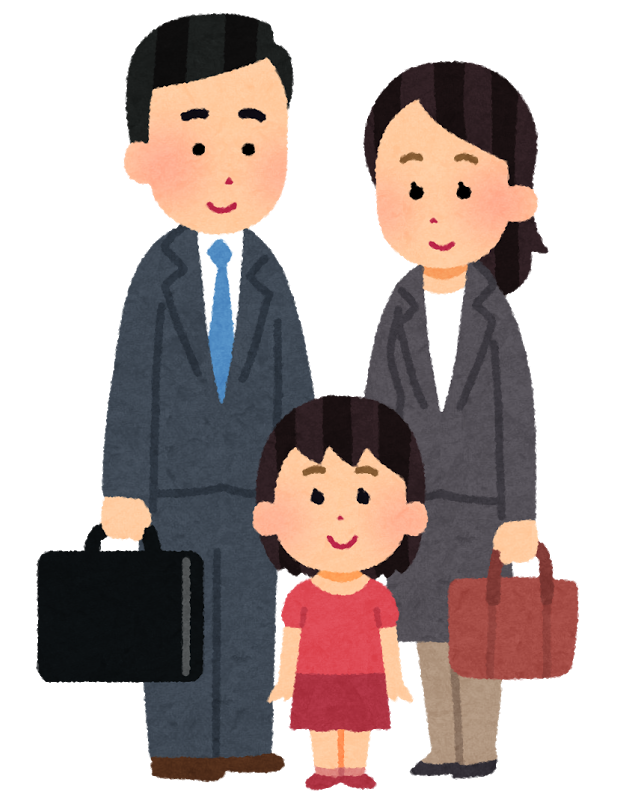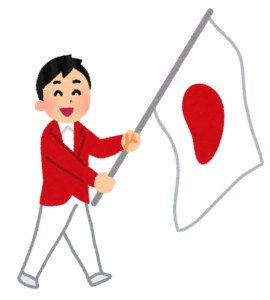専業主婦というカテゴリーはここ50年程度で現れた新しい概念に過ぎないという話です
おはようございます。
2018年2月の配信記事です。
政府の女性活躍の大号令の一方、専業主婦層が潜在的な疎外感に似た感情を抱いているという新聞記事がありました。
しかし、日本における専業主婦の比率は未だ30%台と、いわゆる先進国の中で突出して高い水準です。
一方、北欧の事例ですが専業主婦率がわずか2%程度しかないスウェーデンでは出生率が日本より格段に高いということを見れば、専業主婦が子供を産み育てやすいといった感覚的な議論は全くの錯覚であり、そもそもなんの相関もないのは明らかです。
そして、さらに1970年頃まで遡ると、実は日本の女性の就労率は、当時の欧米諸国に比べても高かったのです。
その後、いわゆる専業主婦層が一般化し、そうしてそうした専業主婦家庭に育った子供たちが今40代を迎えているというのが今の日本の現状になるわけです。
筆者もその子供の一人です。
要するに、ざっと50年前に立ち戻りますと、夫婦共働きというのは普通であり、より時代が遡って近代以前の封建時代に戻ってみても、事例は少ないですが女性の名主も庄屋も、女性の城主(井伊直虎など)だって女性が家督を継いだこともあったわけで土地の所有権も保有していたということを考えますと、専業主婦なるカテゴリーは、長い日本の歴史を眺めても、非常に限られたたかだか50年程度(半世紀)のトレンドであったに過ぎないということに他ならないのです。
そうして、そのトレンドはほぼ終了し、これからは元々の原理原則、働く能力と意欲のある者は女だろうが男だろうが普通に働く通常の世の中に戻っていくのではないかと思って見ています。
明治以前の日本で一番多かった家業は農業であったでしょうが、当然皆共働きです。
おそらく、高度経済成長を成し遂げた昭和のベビーブーマーのみなさんの家庭において、お父さんがサラリーマンで出世していくことを子供にももう一度勝ち組サラリーマンな人生を望みその手助けをするために母親が家庭に入って子育て+子の教育環境整備を担ったという、歴史的に見て非常に特異な時代ではなかったかと思うのです。
そして、第一次産業がメインの経済主体においては、当然共働きの方が多かったはずです。
ところが、サラリーマンがメインとなり、会社の異動や配置転換により、日本全国どころか世界中を家族丸ごと移転するという転勤族という事実上の職業国内移民制度があり、北欧諸国のように社会福祉および女性のサラリーマン社会への進出を強力に促す仕組みや法制度を持たなかった日本の高度経済成長社会においては、自然とサラリーマンを続けない女性を専業主婦になるしかならないように仕向けてきたわけです。
このあたり、共働きという、原理原則に戻るゆるやかな意識改革が進んでいるところ、待った無しの少子化を少しでも食いとめるべく、政府や公共部門の強力なリーダーシップが必要なのですが、なんと、その司令塔であるべきの国会の政治家のみなさん(いわゆる国会議員)の多くが、田舎出身の(そして選挙権も2倍以上持つ有権者に支えられた)老年男性であり、そうした昭和後期の一時期の歴史的には特異な事実上の制度を金科玉条にして、こうした「普通に元に戻る」方向に猛烈に反対し、女性は子育て第一といった訳のわからないことを言いだしているというのが大方の概観なのであろうと考えています。
子育て第一を本当に掲げるならば、夫婦とも能力と意欲の限り働き収入を得て、そして多くの子供を持ち教育させ、そして少子化に喘ぐ日本を救っていただく方向になるべきなのです。
しかるに、これでは、日本が滅ぶのが早まるだけなので、もう少し若い有権者や普通な世界が見えている賢明なる有権者の方々には、こうした老害田舎議員のような方々の主張については、よく吟味いただき、適切な投票行動なりに繋げていただければと思います。
普通が一番だと普通に考えているのですが普通じゃなく異常と言われる筆者からは以上です。
(平成30年2月27日 火曜日)