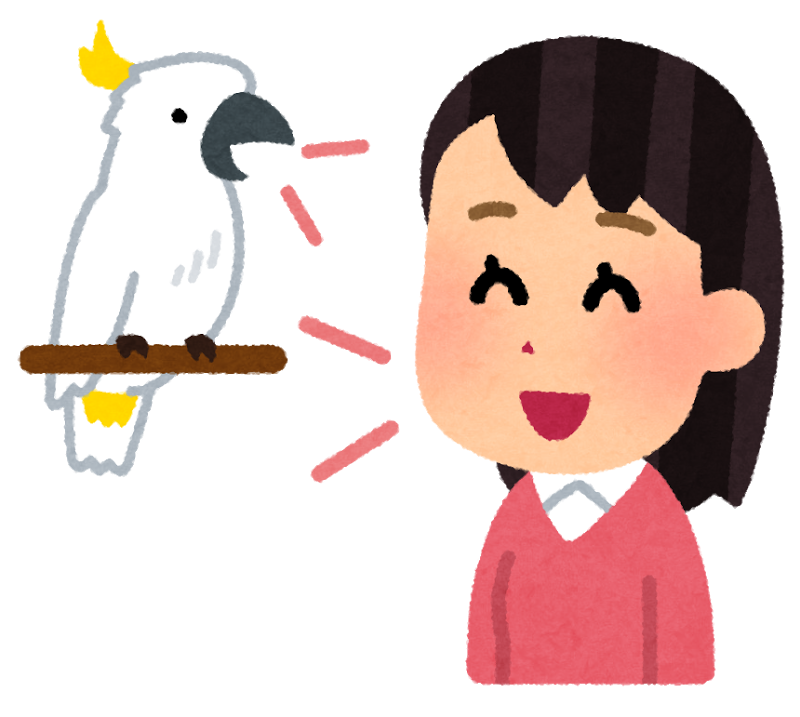社交性やコミュニケーションスキルは大切だがそれだけではだめだと思うという話
おはようございます。
2017年12月の記事です。
社交性はあまり高くないという自己評価の筆者です。
社会人になってから、たくさんのコミュニケーション機会、例えば飲み会や食事会に、はるかな回数出てきて早20年が経過しているのですが、ビジネスや事業、勉強や自己啓発を続けるには同じくらい、いやそれ以上に説明能力や論理性のほうが必要であるということがようやくわかってきたような気がします。
すなわり、一見社交的に見えるのですが、その中の人の実際の論理的思考力が弱かったり、理解力が不足しているような人がいた場合、その人は社交性を磨く前に、自らの説明能力の向上に費やした方が良いのではないか、はるかに有益ではないかと思えるのです。
説明能力が不足していて論理的な説得材料を提示できない話者が、いくら社交性やコミュニケーション能力を増やしたりコミュ力を向上させても、やはりビジネスにはならないのです。
説明能力は、コミュ力では代替できない、そもそもそれらは別の能力だから、という説明になります。
この点、とにかく飲めばわかるという昭和型上司の元で働く場合、論理的な人であるほど非常に働きにくくなります。
飲めばわかる、休日に上司の家にいってバーベキューパーティーに出て気の利いたことを言う、タバコ部屋でよもやま話ができる、といったコミュニケーション機会こそ最善、と信じる手合いや勢力は結構今の社会にも残存しているのかもしれませんが、社員同士の会話を増やすことが重要というのと、会社が成果を出せるような仕組みにするということは実際あまりリンクしないのではないかとすら思えてきました。
同じような話で、「社内のコミュニケーション」と同じくらい「社員のモチベーション」というのも重視される傾向があります。
もちろん、モチベーションは重要です。
息をするのも面倒、というくらいモチベーションが下がれば仕事どころではありません。
しかし、組織目標である売上や利益、成果といったものに直結する組織態様は、モチベーションでもコミュニケーションそれ自体ではありません。
それらは、手段であり結果ではないかと思っています。
組織に第一に必要なのは、事業目標と、それに至るための手段、そしてそこに向かうための日々の習慣や心構えの方です。
この軸から、「詳しい人に話を聞きに行く」「事業目的をやる気が出るものに設定する」といった動きが出てくれば、一見コミュニケーションやモチベーションが事業目的のように思うこともあるかもしれませんが、それは違うと明確にわかるのではないでしょうか。
会社が活性化するから、会話を増やしましょう、といった場合、会社を奈落の底に突き落とすような壊滅的な事業成果を突きつけて、会社が火の車、蜂の巣をつついたような阿鼻叫喚状態になるのも活性化ということになってしまいます(某原発と半導体を事業の柱に据えていた世界的に有名な日本の家電メーカーの例を引くまでもなく)。
会社や組織は活性化それ自体ではなく、事業目標に沿った成果を追求する場であり、コミュニケーションはそれ自体単なるコストに過ぎません。
同じ単位時間で、手段としてできるだけ濃度の高いコミュニケーションを行う必要があるのです。
それが、昨今言われている働き方改革ではないかと思います。
といいながら実は会社でダラダラしてよた話をするのがとても好きでたまらない、昭和なサラリーマン筆者からは以上です。
(平成29年12月13日 水曜日)