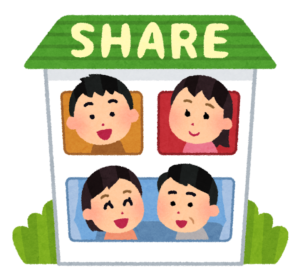(2019/10/02)日本の少子化は地方における初等教育(義務教育)を恐ろしく毀損していると感じた話です
 |
| 税率が異なる駄菓子(消費税軽減税率「大喜利」より) |
おはようございます。
2019年10月の日本の教育に関する配信記事です。
日本の教育については、それなりに問題意識を持っておりまして、現在は、日本の中で極めて優等な教育を受け、官僚機構に所属することを難しい試験合格により許された人たちは、2019年10月から導入された消費増税と軽減税率という、相反する制度の同時導入において、上記のような「緻密」で「芸術的」な、世界も驚く明確なルールを作ることができる「能力」を備えているわけであります。
今一度、「税率が異なる駄菓子」の大喜利をご覧下さい。
日本の優秀な教育を受けた人々の多くは、今はこのような「お金」にならない作業をしていますが、いよいよ日本がさらに危機的な状況になれば、きっと一斉蜂起して、日本社会文化を一気にマネタイズして、日本を救ってくれる、そうした「余力」を持っているのだ、「準備運動」をしているのだと、国家公務員上級職試験は受験しませんでしたが代わりに国会議員政策担当秘書の資格は試験で取得した筆者などは思うことにしております。
このような、世界に自慢できる緻密な官僚機構が日本にあることを、まずは誇りに思って良いのです。
この「機構」維持にどれだけのコストがかかっているか、は別にしまして、とにかく能力としては非常に高いものを「現出」できている、というよい事例でありますので、まだまだ日本は大丈夫、と言えそうです。
こうした「ルール作り」と「現場への徹底」「運用」のコストを上回る税収となり、社会保障費等を充実(補填)させ将来の不安を解消すべく、日本国を想って筆者も些少ながら、バンバン消費活動に勤しむことにいたします。
しかしながら、毎年の甲子園球児の熱戦と非常にレベルの高い試合に感動する如く、忘れがちな点ですが、「少年野球人口」自体が急激に減っていること、特に中学の軟式野球部の廃止や活動停止が止まらないことに気づいている人々はまだ少ないのではないでしょうか。
これは、サッカーやバスケットボール、ラグビーといった他のスポーツの人気が高まったということによる、児童生徒の奪い合いが激化した、ということもあると思うのですが、より問題なのは、もはや課外活動、特にチームスポーツを継続的にやらせるだけの人的体制的な余裕が、少子化が止まらない日本全国、特に地方において失われつつある、ということなのです。
少子化が進むと、まずは「遠くから通える可能性が高い」中学校が統廃合されます。
中学校が統廃合されると、そこからの卒業生をお客として当てにしている、地方の商業高校、工業高校や普通科高校といった「地元の高校」の入学生徒が激減し、そして廃校となります。
そうして、例えば、筆者の本家がある上天草市松島町、といった田舎になりますと、それまでは、歩いてなんとか行ける4キロメートル先にあった中学校が、統合されて、自宅から12キロメートル離れた中学校に、朝夕それぞれ1便しかないスクールバスで通う、ということになってしまうのです。
気合入った男子ならば、晴れた日ならば自転車で通学することも可能かもしれませんが、この行き帰り1便しかないスクールバスを逃せば、自宅の親や保護者に、車で迎えに来てもらうしかないわけです。
これでは、運動系の部活動やら、夜遅くまでやっている塾など、できるわけがありません。
公営バスも、1日2便しかその方面に向かうものがない、というような場合、たとえ21時まで塾や自習室を開けても、生徒を家に返すには、塾の人が自ら車で送迎するしかないわけです。
甲子園や全国中学生大会を目指す野球部の練習やチーム作りなど、できるわけがありません。
本気で東大一直線の塾も、なかなかできないでしょう。
才能は、全国にまんべんなく偏在しているはずなのに、教育の機会は、事実上極めて制限されている、これが日本の将来の国力を著しく減退させる要因でなくて何でしょうか。
唯一、可能なのが、学校のそばに「寮」を併設して、そこで基本寝泊まりしてもらうことですが、勉強にしろ、運動系部活動にしろ、やはり中高生といった心身の成長期にある子供たちをいきなり親元から離れさせるよりは、家の近くの学校に「歩いて」通学する方が良いというのは道理です。
寮生の大阪桐蔭高校と、通学生の履正社高校、どちらの野球部も夏の甲子園全国制覇、という対比もあるように、高校生くらいになってようやく寮生でのメリットが出てくるけれども通学の良さも捨てがたい、というのが筆者の評価です。
ということで、義務教育として公的機関がその義務を負っている中学教育において、統廃合が進みすぎ、朝の時間と放課後という貴重な時間が、「ほぼ通学」に費やされてしまい、大事な課外活動ができない、という環境下に中学生を置いてしまうことの弊害は非常に大きく、タブレットによる授業の深度を高めるべく、学校と家とは違った第三の場所を早急に確保することは、絶対必要な方策だと考えています。
塾にせよ予備校にせよ部活にせよクラブチームにせよ将棋教室にせよ囲碁教室にせよ、中学生にもなれば、家と学校と、その次に自らの居場所となる「第三の場所」が必ず必要なのです。
上記の選択肢は、都会の中学生には取れますが、大都会の子供で、例えば通学に2時間近くかかるような中高一貫校に通わせている親を持つ当の子供も、同じように大変だと思います。
中学3年間、合計1,000日通学の往復。
高校3年間、合計1,000日通学の往復。
これは、たとえ電車の中でも本は読めるといっても、相当のディスアドバンテージであり、苦行です。
こうした、少子化による「公の教育の場」の減少を補完して、全ての生徒に均等な「教育」の機会を与えて将来の日本の国力減退を少しでも防止する、これが今一番必要な教育のテコ入れだと思うのです。
そのために必要なのが、第三の場の確保と、シェアリングエコノミーを利用した通学という行為の効率化、そして、オンラインで場所を問わずに学習ができる自学キットの充実でしょう。
この課題は、日本全国津々浦々の地方にあまねく転がっています。
将来の日本で、税率の計算もできない官僚機構に頼るような残念なことにならないように、今から備えておくべきだと思います。
同じ問題意識を持たれている方、一緒に小さいことから課題解決を図っていきましょう。
ご連絡をお待ちしております。
日本を救うためのバンバン消費活動、ということで、久しぶりにガリガリ君ではなくて単価の大変高いハーゲンダッツアイスクリームを買ってみました筆者からは以上です。
(2019年10月2日 水曜日)
▷▷次の記事は