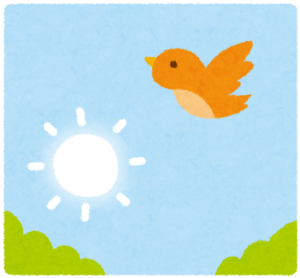久しぶりに近所のバッティングセンターに行ってバットを振りながらで考えた話です
おはようございます。
2013年11月のビルメン王提供の運動に関するブログ配信記事です。
バッティングセンターに久しぶりに行って考えた話です。
バッティングセンターで投げられる球が微妙にずれた場合は仕方ないとしても、明らかにデッドボールに近いようなボール球だった場合、例えば規定の球数には数えないといった配慮をしてくれてもいいじゃないかと思ったことがあります。
技術的に機械で投擲するボールをストライクど真ん中に集めようとすれば、まずボールの「縫い目」を無くす必要があります。
ピストルの弾丸や大砲の球に縫い目はありません。
一方人間のピッチャーはその縫い目に指をかけたりかけなかったりして様々な球種を投げることができるのですが、最もよく知られた球であるストレート(ストレートも変化球の一種です)は四本の指をそれぞれ縫い目にかけて上回転のボールを投げて揚力をつけてできるだけ真っ直ぐの球筋にするのです。
糸をひくようなストレートといいますが厳密には重力がありますのでボールは「落ちて」いますが、この落ちる差が少ない球を投げることができる投手は手元でぐっと伸びるストレートで打ちにくいなどと評価されます(個人的に見るのをお勧めするのはやはり往年の巨人軍の江川投手です。2016年現在ならばレッドソックスの上原投手もよいです。)。
さて、バッティングセンターでは機械がボールを投擲するシステムです。
縫い目を認識して人間の指のように引っ掛けて投げるというシステムの開発は現在のロボット技術水準では難しいでしょうから、レガシーな柄杓のようなバネ式かローラー回転による摩擦発射式、または空気による押し出し式といった技術方式になります。
そうすると、ボールの縫い目が球筋に予想しない影響を与え、バッティングセンターでのボールの一部がボール球になってしまうのです。
これを避けるには縫い目のないつるつるのボールをバッティングセンター専用に開発し、それで投擲することになるでしょう。
しかしストライク確率が高まっても所詮それは実際の投手から放たれる生きた投げる球とは別物になってしまい、かえってバッティングフォームを崩してしまいそうです。
野球に限らずスポーツの専用マシンによる強化トレーニング全般に、かような「別物になってしまう」というリスクが潜んでいることを感じられたので本稿はこれで終わります。
バッティングもピッチングも不調な筆者からは以上です。
(平成25年11月7日)
▷▷次の記事は