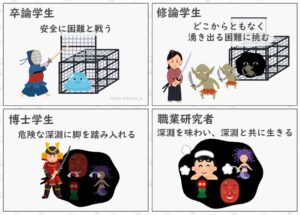監査役制度

日本のコーポレートガバナンス改革:その1-監査役制度の変遷-
2020-06-12
【論考】
日本コーポレートガバナンス研究所 理事長 若杉 敬明
第一部 日本の監査役制度-ドイツの監査役制度と英米流の取締役会制度の狭間で-
監査役の制度を定めたのは1890年(明治23年)制定のいわゆる旧商法である。旧商法とは、商人の営業、商行為その他商事について定めた日本の法律であるが、ドイツ人の法学者・経済学者であるヘルマン・ロエスエルにより起草された。 それに対して民法はフランスの法典を手本として定められていたため、商法と民法との整合性が議論になり、1899年(明治32年) 新商法公布された。
旧商法においては、株式会社の運営体制として、基本的意思決定を行う株主総会、業務執行を行う取締役、監督を行う監査役の3機関置かれた。取締役は必ず3人以上必要とされ、かつ、取締役会の設置が義務づけられていた。ガバナンスの観点から注目すべきは、監査役就任の資格は株主に限られていたことである。まさに株主のガバナンスである。監査役は、取締役の業務監視権および株主総会招集権の二つからなる経営監督権限と会計監査権限とをもつ。監査役の人数については定めがない。なお、1899年新商法では、総会招集権限と取締役の会社代表訴権および取締役の自己取引(利益相反取引)の承認権が新たに付与され、監査役の権限が強化された。
旧商法および新商法で監査役に与えられた権限は、経営監督権限と会計監査権限である。監査とは監督&検査からの造語であると言われる。監督とは経営者に対して事前に指図することであり、検査とは経営に対する事後の検査である。英語では、auditは通常会計検査を指し、internal auditというと内部で行われる会計検査を言い、外部の公認会計士が行う会計検査はexternal auditあるいは単にauditという。なお、最近の米国では、internal audit部門は経営検査も行うようになっている。
1950年(昭和25年)英米流の取締役会制度が導入され、経営監督は取締役会による自己監査が原則になり、監査役の職務は会計監査が基本となった。監査役の権限は大きく縮小されたわけである。しかし、証券取引法(現在の金融商品取引法)との整合性を図るために、監査役に再度業務監査権限が付与された。これにより、業務執行に対する取締役会の監督権限と監査役の監督権限という二重性が固定され現在に至っている。しかし、取締役会の自己監査が形骸化していったことから、その後、粉飾決算や企業不祥事などが社会的な問題になる度に、監査役の権限強化と地位強化(独立性の確保)とでガバナンス問題の解決が図られてきた。明治時代に定められたドイツ流のガバナンスシステムが生き続けていたのである。新しいガバナンスシステムの導入には、委員会等設置会社の導入を決めた2002年(平成14年)商法改正を待たなければならなかった。
このように日本語の監査という語は旧商法以来1950年商法改正まで、「経営監督+会計検査」を意味していた。米国では、事前の経営監督は「取締役」が行い、事後の会計検査はinternal auditorおよびexternal auditorが行う。現在の米国の取締役会にはaudit committeeが必置機関であるが、その役割は、事後の検査人であるinternal auditorおよびexternal auditorの独立性を検証することであり、会計検査を行うことではない。話が込み入って来たが、本来の”audit”は明治以来日本で制度化されてきた監査役の「監査」とは異なり、経営者(CEO)の部下であるinternal auditorあるいは外部のexternal auditorが行う事後的な会計検査である。
◆ 日本の監査役が米国の会社を訪問し名刺交換するとき、肩書きのAuditorをから低く見られる傾向があり、監査役はプライドを傷つけられることがよくあったと言われる。日本の監査役は株主総会で選ばれる役員でむしろ社長より上の立場であるのに、auditorがCEOの部下である米国の会社ではそう見てくれないので、監査役のプライドが痛く傷つけられるのである。米国には日本のような監査役制度はないのである。audit=監査ではないのである。もっとも日本の会社のシステムが知られるようになってきて、最近は正しく理解してくれるアメリカ人もいるようである。
1950年の商法改正で米英の取締役会制度を導入したときに、監査役の制度を整理すべきであったのに、そのまま残したために紛らわしいことになってなってしまった。近年のコーポレートガバナンス改革の流れにおける経営監督は取締役の役割である。取締役会にaudit committeeがあるが、その役割はauditorsの独立性を事後的に検証することである。自ら会計検査をするわけではない(それゆえaudit committeeが行う財務諸表のチェックはauditとは呼ばずにreviewと呼ばれる)。
日本の監査役は、経営監督権限と会計監査権限とを与えられてスタートした。異質な二つ機能を担った日本独特の制度であると言われている。監査役の監査はauditと翻訳してはいけない、あるいはauditを監査と翻訳してはいけないのである。
第二部 監査役会制度の変遷
1890年旧商法制定(明治23年)
・株式会社においては、基本的意思決定を行う株主総会、業務執行を行う取締役、監督を行う監査役の3機関置かれた。取締役は必ず3人以上必要とされ、かつ、取締役会の設置が義務づけられていた。
・監査役の就任資格は株主に限られ、監査役は取締役の業務監視権および株主総会招集権からなる経営監督権限と会計監査権限をもつ。監査役の人数については定めがない。
1890年商法公布(明治32年)
・会社代表訴権および取締役の自己取引(利益相関取引)の承認権が新たに付与され、権限が強化された。
1938年(昭和13年)改正商法
・監査役の資格について、取締役及び支配人の兼任禁止が加えられた。また、取締役員に欠員が生じた場合にはその職務を代行する事が規定された。
1950年改正(昭和25年)
・英米法的な取締役会制度導入にともない監査役の権限が縮小され、業務監査権限は取締役に委譲され会計監査に限定された。株主であることが監査役就任資格であったがその制度は廃止された。他方、株主には次のような権限が付与され株主の権限が強化された。・株主代表訴訟提起権、違法行為差止請求権、会計帳簿閲覧請求権、株式買取請求権など。
◆ ガバナンスの観点から興味深いのは、従来の商法では、監査役が代行していた株主のガバナンスが、株主自身の戻されたと見ることができることである。1945年から47年に掛けて「侵略戦争の経済的基盤になった」として財閥解体が行われた。財閥が保有する株式は、「証券民主化」のかけ声の下、給与などの形で国民の手に渡り、個人の持ち株比率は一時60%を超えたと言われる。ところが、当時の国民は貧しかったので株式を手放さざるを得なかった。いわゆる乗っ取り屋などがそれを買い占め、買い占め屋は企業にそれを持って行き高値で買い取ることを要求する(米国のgreen mailer)という事件が相次ぎ企業は悲鳴を上げた。そこで、財閥解体とともにとられた企業の株式保有禁止が解禁された。企業の株式保有は財閥により財閥企業間の循環投資や持ち合いに利用されていたためである。これにより企業間の株式持ち合い急速に拡大した。ちなみに、これは第一次の持ち合いブームであり、第二次ブームが1960年代OECD加盟後に起こり、日本の株式持ち合い体制が定着した。
◆ 本来であれば、ガバナンス体制の強化のために英米型の取締役会制度の導入が図られたのであるが、動じに行われた財閥解体・証券民主化そして企業の持株禁止解除という諸措置により、本来の株主のガバナンスが希薄化されるというまったく逆の結果になったことはまことに皮肉な結果であり、日本にとって不幸な結果である。とくに、証券民主化がむしろ国民が株式から目を背ける国民風土を形成したことは現在に至って深刻な影響を与えている点は深刻である。
★ 1965年(昭和40年)、山陽特殊製鋼倒産事件(倒産により粉飾決算が発覚)が発生し取締役会による経営監督の機能不全が露呈されたことから、商法が改正された。
1974年改正(昭和49年)
・再度、監査役に業務監査機能が付与された(小会社を除く)。このことから取締役会と監査役の二つの経営監督機関が並立することになった。ともに株主総会で選任された取締役と監査役とが重複した機能を持ち、世界でも類を見ない独自の制度である。ただし、監査特例法により資本金1億円以下の小会社においては、監査役は従来通り会計検査機能のみである。大会社においては、会計監査人による会計監査を義務づけられ、監査役の会計監査と会計監査人の会計監査とが併存することになった。また、解任時の意見陳述権の付与、任期延長などにより監査役の地位強化が図られた。
1974年 商法特例法(監査特例法)制定
・大会社においては監査役の他に会計監査人(公認会計士または監査法人)による会計監査を義務づけられたが、小会社においては監査役の権限は会計監査権限に限定された(業務監査権限はない)。
★ 1976年(昭和51年)戦後最大の疑獄事件「ロッキード事件」が発覚した。米ロッキード社から日本の政界などへ流れた資金をめぐり、田中角栄元首相ら政治家、丸紅、全日空の幹部ら計16人が受託収賄、贈賄などの罪で起訴された。さらに1978年(昭和53年)には、ダグラス・グラマン事件等の会社が不正支出をしていた不祥事が明るみに出された結果、このような不正を会社が自治的に防止できるような措置を講ずるため次のような商法改正がなされた。
1981年(昭和56年)改正
・監査役の地位強化が図られ、会計監査人の株主総会による選任、監査費用請求などの権限が付与された。かつ、監査役制度の充実が図られ、商法特例法上の大会社に複数監査役制度および常勤監査役制度が導入された。なお、商法特例法の大会社の範囲が拡大された(資本額のほかに、負債総額も基準にする)。
★ バブル崩壊後の1991年(平成3年)6月に発覚した証券・金融不祥事件(証券会社の一部の投資家に対する損失補填、金融機関の偽造の預金証書を担保とする融資)を契機として、監査制度を充実する改正がなされた。
★ バブル崩壊後日本経済は低迷し
1993年改正(平成5年)
・監査役の地位強化(監査役任期の伸張2年→3年)がなされるとともに、監査役会制度が法定化され、3名以上の監査役設置を強制し、大会社においては1名以上を社外監査役とすることが義務づけられた(中・小会社では1人以上)。
★1999年 東証 ①「コーポレートガバナンスの充実について」を上場企業に要請するとともに、②決算短信でコーポレートガバナンス施策そ開示を要請することを要請。
2001年改正(平成13年)施行は2005年(平成17年)5月1日から
・議員立法による改正が行われ、再度、監査役の地位強化が図られた。➀監査役任期の3年から4年への伸張 ➁・取締役会への出席および意見陳述義務の明文化、③辞任時の意見陳述権、④選任における監査役会の同意権・提案権等が付与された。また、商法特例上の大会社には、社外監査役の人数の拡充(1人→半数以上)が義務づけられるとともに、社外監査役の社外性が厳格化された。
(「21世紀のガバナンス改革-日本のコーポレートガバナンス改革:その2」に続く)
2021.12.1/2019.10.10