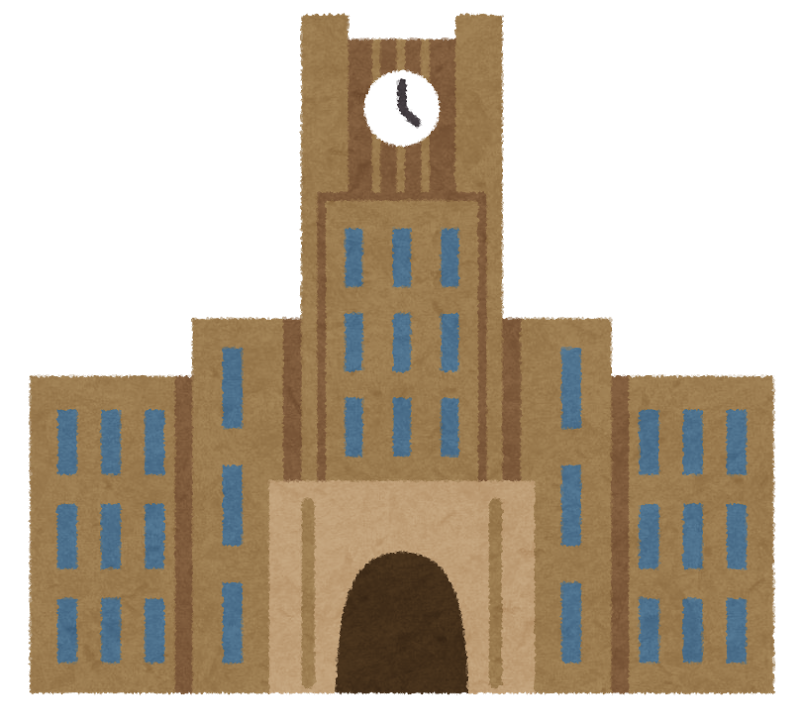日本国憲法において最も改正議論が本来起こらなければならない部分について(私見)
おはようございます。
2018年2月の配信記事です。
筆者は大学は文系学部(法学部)に学び、それなりに勉強したことも勉強しなかったこともありますが、昨今のテクノロジーの進化は文系学部のほぼ全ての講義というものを駆逐しつつあるとすら感じております。
もはや、大学の授業、教授とはオンラインでほとんど代替され、わずかに実験系やシミュレーション、フィールドワークが必要な理系学部の一部のみが生き残る場になっていくのではないかと本気で考えております。
もちろん、それぞれの学生が学ぶ場としての大学が大切であろうとは言えるのですが、板書にスクール形式のいわゆる授業というものは早晩消えて無くなるだろうな、と思うわけです。
一緒に学ぶ学徒や教授が一緒になんらかの議論をするとしても、それはすでに前提とされている知識や技能が与えられている状態で行う、いわゆるフィールドワークや議論討論、ゼミの場やプレゼンテーションといった形になるのでしょうか。
さてそんなことを考えながら、本日は最近言われるようになってきた日本国憲法改正の風潮において、筆者が憲法学徒(一応大学の憲法の単位はたった一つの「優」であります)の端くれとして感じている点を申し上げます。
日本国憲法第89条(公金その他の財産の支出)
本来、最も改正議論が起こっていなければならないのは、天皇に関する章でもなく、戦争放棄の第9条でもなく、いわんや憲法改正手続自体を規定する第96条でもなく、やはり第89条(公金その他の財産の支出)であろうと考えるのです。
時代にそぐわない条項として、これ以上のものはないと思うわけです。
原文にあたります。
日本国憲法 第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
とありますので、本来、宗教団体性の強い政党に対する政党助成金交付は当然にアウトですし、私立大学といった宗教性(先覚者)を多少は帯びるもの、もしくは宗教性が全くなくても「公の支配に属しない教育の事業」であることは明確であります。
さらに慈善、教育若しくは博愛の事業で「公の支配に属さないもの」など、NGOや町内会を考えればいくらでも出てくるのですが、そういったものに対する補助金や助成の一切が違憲となるのはどうみてもおかしいわけです。
現在、第9条の合憲判断などよりもっとずっと飛躍した論理、すなわち、「公の支配」という領域を限界いっぱいまで解釈上広げることにより、私立大学や私立高校に対する助成金や、NGOに対する補助等、さらには特定の宗教団体との関係性が事実上濃く認められる政党への政党助成金など、これらすべて「公の支配」にゆるいながらも属しているのだという解釈です。
合憲にしなければいけないので、これが通説です。
例えば、私立学校も色々な法律に服しているし、広い意味で、「公の支配」に属しているという解釈です。
しかし、これでは、「公の支配」は、単に「日本国内」にその存在がある、という程度の意味しか持たなくなり、この第89条は一体何のためにあるのだということになるのです。
こうした、論理的な破綻が明らかな条文の適切な時代の要請に即した「改正」を通じて、日本国が、日本国憲法の目指す自由な世の中になっていくことを望みますし、その議論の過程で他の憲法改正候補についての論点が整理されることが何よりも国民にとっては大切な共通の財産になることだと思っています。
たまには、真面目な話もすることができる筆者からの吹っかけ議論は以上です。
(平成30年2月21日 水曜日)