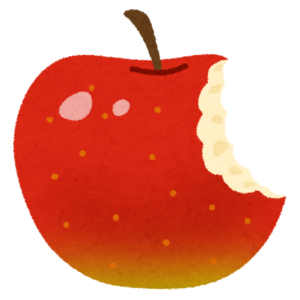地域格差と単一通貨の相克(ユーロという通貨の信認を題材に議論)
おはようございます。
2017年2月の記事です。
広大な欧州大陸において、ヨーロッパの人たちが通貨統合を成し遂げてずいぶん経過しますが、2017年は、改めてユーロという通貨の信認が揺らぎつつあるのを感じてなりません。
なぜこのように感じるか、少し考察してみました。
欧州大陸を広く包み込む国家共同体ユーロにおいては、勤勉なドイツ国民も、もっと生活を楽しみたいラテンな国々(ギリシャやイタリアやスペインなど)も、同じ通貨で仕事をします。
勢いせっせと仕事して貯めるドイツとその他の国々で、経済力に差がついてくるのは仕方のないところです。
逆に、ドイツも他の国に自国製品を輸出することで利潤を貯めますから、ドイツにとっても域内ユーロの国々はお客さんとして必要なのです。
「怠惰なだけ」では経済格差は説明つかない
ですから一概にギリシャやイタリアやスペインの国民が怠惰だから、とは言い切れないのです。
安くて性能のよいドイツ製品をせっせと買うことでドイツの経済発展に寄与した、という良き消費者の一面も持つのです。
ここで大変なのは、自国でのGDP内で自国借金を完結せよ、というユー
ロ統合の縛りです。
日本において、都会が地方の財政的支援をするのは常識となっておりますが、それが厳しく制限されているところから、今日のような厳しい状況にたどり着いたわけです。
日本において、例えば北海道や九州が域内経済ですべて完結せよ、としたら大変なことになります。
我々田舎の者は、東京や関西京阪神に労働力を提供し協力をしているのだ、東京のような都市で上がる利潤の一部を地方に還元せよ、というのは地域格差解消という名の下、ずっと高度経済成長期から進められていることです。
ユーロの国々にはそのような潤滑油的機能がないために、今日のような状況になっているとも言えます。
そういう意味で、日本の田舎は文句も言わずに(人手を吸い取られながら)よくやっているとも言えます。
私も田舎の者ですが。
是非東京大阪のような大都会にはグローバル競争の中しっかり稼いでもらって、国会を通じた再分配システムで、地方を潤してもらいたいと本気で考えています。
そのために、地方は都会に人的資源をせっせと「拠出」しているのです。
ただし、全国的世界的な少子高齢化の世紀の到来を受け、そろそろ地方も小規模国家も、自分自身のことは自分で考えるようにしていかなければならないのかもしれません。
怠惰なことは認めざるを得ないサラリーマンの筆者からは以上です。
(平成29年2月8日 水曜日)