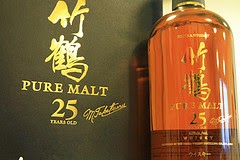かつて日本がジャパン・アズ・ナンバーワンといわれた時代が確かにあった
 |
| ジャパン・アズ・ナンバーワン |
おはようございます。
2014年11月の、かつての日本の栄光を昭和生まれのおじさんが語るという配信記事です。
「ジャパン・アズ・ナンバーワン」。
Japan As No.1という本がかつてベストセラーになりました。
1979年にアメリカの社会学者でかつ(ここが重要)ハーバード大学教授のエズラ・ヴォーゲルという人が、日本について好意的に評価した著書でした。
この書には、いわゆる終身雇用や人を切らないといった日本型経営によって高度経済成長がもたされたことを、奇跡と賞賛し、これからはNO.1としての日本の時代がやってくるという予言をした書として知られました。
日本人は、まだ「ニューヨークへ行きたいか!」という視聴者参加型クイズ番組くらいでしか、アメリカ本土なるものをほとんど知らなかった時代ですから(それだから国民的娯楽漫画であるドラえもんにおいて、スネ夫がアメリカや欧米帰りを吹聴していたのです)、(中身は置いておいて)東大を遥かに超えるなんだか偉くて権威がありそうな「ハーバード大学」の現役教授が書いたこの本に飛びつきました。
よくこんな国とその昔ガチンコで戦争したものです。
外からの評価で、内の見方をころっと変えるのは、有史2,000年、我が国の得意とするところのようです。
この本は、2度のオイルショックに見舞われた1970年代を省エネ技術や持ち前の勤勉さという国民性のパワーで乗り越えようとしていた頃を振り返り、No.1としての日本を諸国も見習おうと呼びかけているわけですが、一つだけ今の日本と決定的に違う環境を申し上げると、非常に顕著な「人口ボーナス」の人口構成であったというところです。
若い人のほうが年寄りよりも絶対的に多いという綺麗なピラミッド人口構造をしていた1970年代の日本にとっては、普通の人でも5年も働けば、その5年で沢山の後輩や部下が入ってくるという幸せな時代だったわけです。
タイトルは別にして実質的な昇進も早かったし、課長や係長のタイトルで、かなり会社の重要な案件を任されるといった状況だったと思われます。
今は、少子高齢化の「人口オーナス」の時代ですから、若い労働力や後輩、ましてや部下などが豊富に入ってくるという環境には全くないのです。
同じ仕事をただ淡々とやっているだけでは当然給料は増えないし、何らかの付加価値を紡ぎださねばならない時代になりました。
今の働く世代は、かなり間延びした長期間の間において、今ある仕事や労働に従事していかなければならない(若い人が代替してくれることはない)という状況なのです。
それに加えまして、テクノロジーの進化は日進月歩であり、今まで普通にやっていた仕事がテクノロジーに取って代わられるというリスクは極めて高まっています。
作業を機械に代替させるという以上に、業務そのものをプログラムが代行してしまい、そちらのほうが正確で速いという時代に我々は生きているのです。
Googleやマイクロソフトの代表が言っているのは、変な予想ではなく、時点を将来にした厳然たる事実と言えましょう。
なかなか厳しい時代に生きているなと思います。
ずっとジャパン・イズ・ナンバーワンじゃないのかと思っていた時代遅れの筆者からは以上です。
(平成26年11月8日 土曜日)