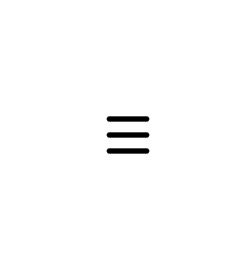自分用講義メモとしても有用なので建設業界の概略を記載しておきます
 |
| ダムの放水 |
おはようございます。
2014年4月の建設業界に関する配信記事です。
不動産業の端くれにいますビルメンテナンス業界の筆者ですが、そもそも維持管理すべき建物がなければ商売になりません。
そこで、どうやって建物ができるのか、その元をたどった建設業界というものを一度おさらいしておこうと思いまして、以下自分用メモ代わりに記録しておきます。
まず、建設業は大きく建築工事業と土木工事業に分けることができます。
また工事の種類として、発注者で区別した公共工事と民間工事とがあります。
縦2つで横2つ、何かと研修などによく出てくる得意の4分割です。
建築工事業は、いわゆる一般のビルや建物ということでイメージがつきやすいですが、土木工事業は、道路や堤防の造成、橋梁の建築、地面基礎の埋め立てや干拓、河川の護岸及び河床の整備などをコンクリート、木材、鋼材、土石などを使用して行う工事と定義されます。
国土交通省から出ている2010年度建設総合統計年度報によれば、建築工事の出来高は約23兆円、土木工事の出来高は20兆円ということです。したがって、我々消費者が街でよく見るような建設工事高は、工事全体の半分もなく、それ以上の工事として土木工事があるということになります。
土木工事の割合が多い
これは筆者にとっては新しい発見でした。
さらに、建築工事の発注者のほとんどは民間であり、公共工事は1割程度しかないのに比べて、土木工事においては、実に7割もの出来高が公共事業として行われているということです。
ですので、土木工事業とは、まさに公共事業の実施に依存しているというわけなのです。
最近、国土強靭化と称して公共部門からの土木工事の発注が増えていると聞きまして、むしろ街の建築工事に回るべき工事職人がいなくなっているという話も聞きます。
筆者のさる知り合いのゼネコン業界の方も、街なかの建築工事から山奥のダム工事に配置換えされたようです。
スーパーゼネコンと呼ばれる大手の建設会社は、当然土木部門も建築部門も持っています。
しかるにこの2つの部門は、宗教で言えば同門なんだけど異端同士というような、なかなか相容れない文化と考え方を持っているようです。
経営者であった大物のOBに話を聞いたこともありましたが、部門毎の独立志向が強く、全社的に統合しするマネジメントは大変難しいらしいとも聞きました。
このような大きな仕事がある一方で、建物の設備管理をしながら、時折小修繕や営繕工事を地道に行っているビル管理会社もあります。
大口も小口も等しく仕事として大切にすることでこの業界は成り立っています。
研修がてらの雑記は以上です。
(平成26年4月21日 最終更新:平成28年4月21日 木曜日)