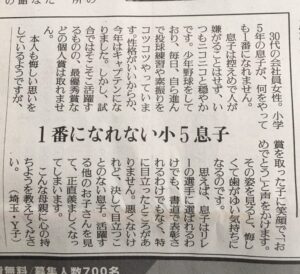神道と仏教

私見です
筆者は、所謂「神武東征」は、卑弥呼の死後3世紀の後半から4世紀にかけて卑弥呼の子孫が九州北部(邪馬台国を含む周辺連合国)で壮大な準備を整え、宇佐を出発港として始まったと推論している。
どうして時代の乖離がシナリオとなっているのか?ここでその独創的な推論を共有します。
仏教伝来から乙巳の変(大化の改新なる名前で潤色されているけど単なる大王殺人クーデター)までで、伝来した仏教は、政治に登用される形で残り、且つ本来の神道もそのまま天皇家の威厳と共に残ったと考えております。
仏教に神道を先んぜさせるための日本神話という仮説
ここで天皇家は、仏教を政治に登用するにあたり神道の優越と威厳を守らなければならないわけであり、これ即ち「神武東征によるヤマト王権」の誕生が、仏教の開祖「仏陀の誕生(BC566年とされる)」より先に完了していなければならないとなるわけです。
これが、天武天皇が編纂する記紀のシナリオの年代のみなもとであると私は推論します。
それが故に、神武天皇のあと2代から9代まで(綏靖天皇から開花天皇)欠史8代を作り、崇神天皇から神功皇后(女王卑弥呼と目される)まで、時代調整と日本武尊などのシナリオ調整が生じていると思うのです。
もちろん、趣味全開の独創的な推論であるが、このように考えると私の中では合点がいくのである。
もう一度神武東征のあらすじを調べてから、次回は、神武東征にかかわると思われる神代にいて述べてみたいと思っています。
死ぬまでに、何とか日本の古代史についてこれでだいたいわかった、という領域に到達したいものです。