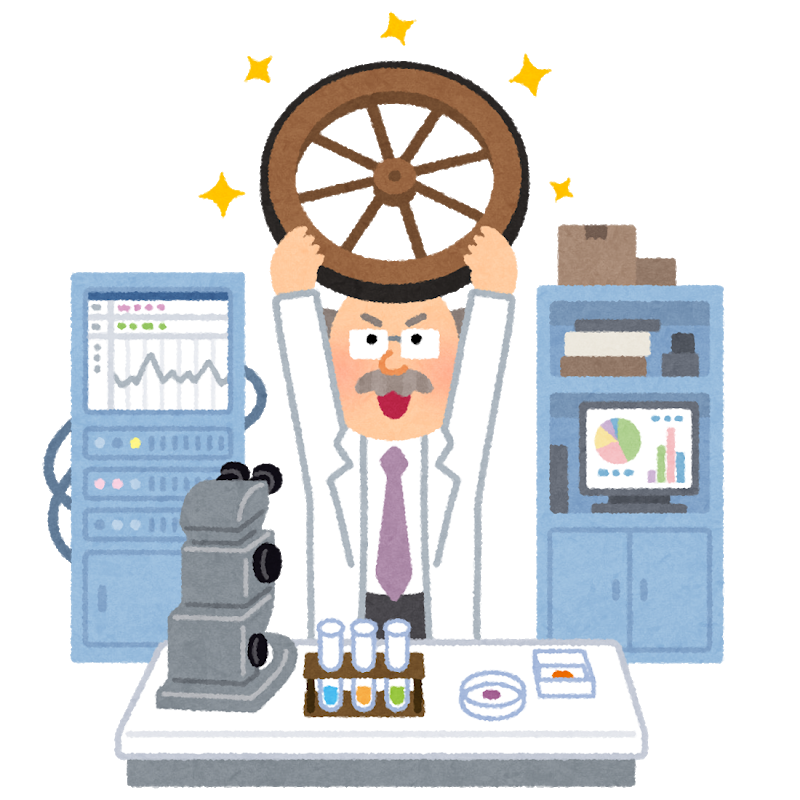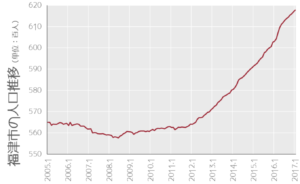社外のネットワークを味方につけて社内を説得する力にするのがオープンイノベーションだと思うという話です
おはようございます。
2019年1月のオープンイノベーションに関する配信記事です。
オープンイノベーションの世界に飛び出して数年経っていますがなかなか成果を出せていない筆者です。
オープンイノベーションの基本は、社内社外のリソースや情報と繋がることです。
とにかく、社内に眠っているノウハウや、社外で取得できる情報を「統合」するためには、まずは知ってもらうための情報発信にかかっていると言って過言ではありません。
しかしながら、情報発信といっても、当然聞く側も何か有用な情報を求めているわけですから、単に「情報が欲しい」という「発信」をしても、それはスルーされるのが関の山ということになります。
ですので、最初は少人数で良いので、気のおけない仲間を社内外から集め、実際に世の事例を真似てみたり、学んでみたりすることで、実際に自分ごと化していくしかありません。
さらに、実際に持ち寄ったアイデアをはじめていくに当たっては、自己紹介の時間やちょっとした打ち合わせの場所などで、短く、シンプルに、事業の「肝」となる話をできるようにならなければなりません。
1分とか30秒でひととおり話すことができる「エレベーターピッチ」と言われるミニ講演で、要点をブラッシュアップしていきます。
そんなことを繰り返していると、もうちょっと詳しく話をしたい、という人が現れてきます。
そんなことがあるのか、と思われるかもしれませんが、そんなもんです。
かのフェイスブックのザッカーバーグ氏も、気になる大学の女の子に話しかけるツールを開発したい、という気持ちから、巨大な同窓会サイトの構築を思いつき、そのアイデアがアイデアを呼び、今のフェイスブックに成長したわけです。
アマゾンの創業が1994年、フェイスブックの創業が2004年といいますから、たったそこそこの20年程度かそこらで、世界は格段に変わるわけです。
そして、そうした社外への情報発信を続けて、社外の協力者や理解者が増えることは、実は社内の、インターナルなマーケティングにも繋がります。
社内にあまりいませんので、なにやってるの?と思われているのではないかと不安になることが多いのですが、社外への情報発信していると、実はそれが社内にも浸透していき、社内で具体的にプロジェクトを進めていくときにとても助かる雰囲気作りになるのです。
新しい話を聞いた社外の人から「おたくの会社では面白いことを手掛けているね」などと言われようものなら、我先に乗っからないと損とばかり、社内の支援者やサポーターが増えていきます。
特に、他社の経営陣(役員とか社長とかオーナーとか)などから、見たよとか聞いたよとか言われると、効果は大きいです。
そして、これはやろうとしていることを売り込むのと同時に、やろうとしている「人」を売り込んでいることなのです。
この人と一緒に何かやってみたい、と思われるためには、人間力を磨くしかありません。
会社の方針なんで新規事業をやっています、というのでは、あまりに悲しく、むしろ会社を使って、私個人はこれを成し遂げたいと思っています、というところに力点を置かなければなりません。
そして、何かを「言っているだけ」の大きく抽象的な話と、「やっている小さな活動」をどう「具体的につなげる」かが腕の見せ所です。
とにかく、新しいことをやるためには、会社の中で社外での活動を理解してもらえないなどと愚痴っていないで、「会社を使う」マインドセットをして、「やらなければならない社内の仕事」は当たり前にこなした上で、外で積極的に活動して信頼係数を上げていくしかありません。
とにかく、楽しく動き回り話まわる、という風に振る舞いたいものです。
最後に、情報発信で最も効果があるのはこうしたブログ記事で自分の考えを述べ続けることなのですが、そこがなかなか「だから読め」とは言えない引っ込み思案な筆者からは以上です。
(2019年1月18日 金曜日)