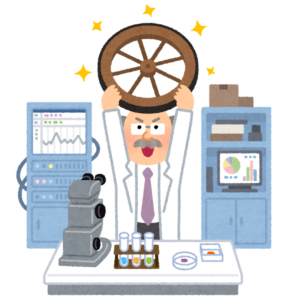2019年1月英国のEU離脱政府案が英国議会で否決され欧州政治経済の不透明さは増す一方になったという話です
おはようございます。
2019年1月の風雲急を告げる国際情勢に関する配信記事です。
トランプ大統領率いる米国と、習近平(終身)国家主席率いる中国との経済戦争の激しさが増していますが、目を欧州に転じてみると、一旦国民投票でEU離脱という決定をした英国も、離脱のやり方についての国内同意が取れず、このままでは2019年3月にはなんの保証も取り決めもないままEU連合から放り出されるという最悪の事態に向かってくるような感じになってまいりました。
英国議会は、テリーザ・メイ首相率いる政権が欧州連合(EU)との間で合意に至った英国のEU離脱協定案を、圧倒的な多数で否決したのです。
支持を訴えて整然としたEU離脱を主導するとしていたメイ政権は、壊滅的な敗北を喫して、窮地に陥りました。
このままでは、2019年3月29日期限の英国のEU離脱に際し、なんの移行措置もないまま英国はEUを期限切れにより放り出されるようなものとなります。
残された方法としては、もう一度議会での再議決を目指す、退陣して次の政権に委ねる、EU離脱を延期する、もしくはEU離脱そのものを取りやめる、というものがありますが、いずれも実現のためには多くのハードルが課せられています。
そもそも英国がEUから離脱しようという国民投票の結果がこうした不確実な状況を招いているわけですが、これは、フランスやドイツ、スペインやイタリアといった大陸国を中心とするEUは発足時の基本理念として、域内でのヒト、モノ、カネ、サービスの4つの「移動の自由」を掲げています。
歴史上大陸に寄り添う島国として、ドーバー海峡という天然の防塁を擁しているUK(連合王国)としては、欧州各国が緊密に統合することで域内の戦争をなくそうという理念、すなわち大陸側の欧州諸国と統合することへの反対意見が根強くあります。
そして、それでもこれまで英国はEUの一員として東欧などから移民を受け入れてきたという経緯があります。
しかしながら、欧州金融危機や経済の不透明さなどで雇用情勢が悪化すると、当然に古くからの英国住民層からの
「移民に仕事を奪われている」
「テロリストの流入につながる」
などという、移民全般への不満が強まったというわけです。
そうして、EU本部に英国の権益を持っていかれることの潜在的恐怖心も手伝い、当時のキャメロン首相がEU残留か離脱かを問う国民投票の実施を表明し、2016年6月23日に投票が行われ、結果は、世界も驚く離脱賛成52%というものだったのです。
この国民投票結果を受け、英国政府は2017年3月29日にEU側に離脱を通告しました。
EU条約では、離脱の通告から2年後にEU法の適用が切れると定めています。
したがって、2019年3月末が離脱の期限となりました。
ただ、企業や行政機関などの活動に支障が出ないように、英国とEUは2020年末までを「離脱移行期間」と定め、現状の規則や法制が適用され続けることで合意したのです。
しかしながら、この移行期間が適用されるためには、当然に英国とEUが離脱条件で合意し、それぞれの議会(英議会と欧州議会)でその政府組織間の合意案が「承認」されなければならないのです。
そして、今回、英国議会がこの離脱条件を否決したということで、もはや、英国とEUとの間に離脱合意が結ばれることは時間的に困難になり、そして、このまま2019年3月末の期限を迎え、離脱合意を前提にした「移行期間」なしの、完全離脱による英国および欧州社会経済への影響は計り知れない、ということなのです。
テスト環境でなんのテストもなしで、いきなり本番稼働しながらプログラムを投入していかなければならないというわけです。
関税についても、商品の認可についても、そもそも人の移動についても、何のルールもなくただEU法の適用が切れる、というこの状況、英国に所属する企業や国民の不便は大変なものだと思います。
しかしながら、国内は全くまとまっていません。
なぜ英議会はせめてもの秩序的な離脱案を否決するのかと言いますと、島国という英国とはいえ、アイルランドと北アイルランド(英国内)における陸続きの国境問題があるわけです。
英国がEUから離脱すれば、英国を構成する一領邦の北アイルランド(首府ベルファスト、英国国教会)もEUから離脱しますが、カトリック教国であるアイルランド(首都ダブリン)は当然EUに残ります。
そして、北アイルランドとアイルランドの間に、陸続きの物理的な「国境」が発生し、そこでのモノやサービスの受け渡しに関税や通関などの実質的な膨大な作業や国境維持管理の経費がかかることになるのですが、そもそも北アイルランドやスコットランド、ウェールズといった連合王国の諸国は、EU離脱は連合王国の主導的地位にあるイングランドが勝手に決めたことであるという意識が強く、俺たちはロンドンには従わない、敵の敵(欧州議会があるEU本拠地である)のブリュッセルは味方、という意識があるというわけです。
北アイルランドを、アイルランド全体に再統合するというシン・フェイン党という地域政党がありますが、この政党は、英国議会に議席を2019年1月時点で下院に7議席保有しているにもかかわらず、伝統的に「英国女王陛下への忠誠を宣誓」することを拒否して、そもそも英国議会に登院せず歳費も受け取らないという態度を貫いている事例もあるくらいなのです。
国と国との約束事を、統合前に戻すという、近世の国際政治では前例のなかった挑戦が始まっています。
ナショナリズムの高まりは、それぞれの国々の意思決定に、合理的ではないノイズを振りまき、世界は混沌とした中に進んでいくようです。
国際政治については素人ですが、かつて日本の国際政治史に巨大な足跡を残し現役教授のまま62歳で世を去った高坂正堯先生(元京都大学教授)の本が出たので、学生時代ろくに聞かなかった講義の罪滅ぼしに読み込んでみようと考えております筆者からの記事は以上です。
(2019年1月17日 木曜日)