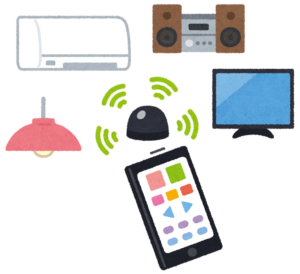寒くなってきた真冬に部屋全体の防寒をするために必要なたった一つの効果的方策について
おはようございます。
2018年12月の急に寒くなってきました季節もいよいよ真冬という記事です。
九州北部に住んでおります筆者などは比べ物にならないくらい寒いところにお住まいの、例えば北海道の友人からの便りには、日中の最高気温マイナス5度、早朝の気温マイナス15度といった表示が並んでおりますが、ここ数日で日本列島は一気に冬模様に変わってまいりました。
冬になると個人的にも気になるのが二つありまして、一つは肌や喉の乾燥、そしてもう一つはそもそもの防寒対策です。
部屋の中が、なんだかスースーして寒いというのはどの家でもあるかと思いますが、その中で、今回は、ビルメンテナンス業の長い筆者の経験の中から、最も効果的な室内の防寒対策について述べておこうと思います。
室内を締め切っていても、どうしても風がスースーするように感じるのは、それは「感じる」のではなくて実際に室内にも弱い気流が流れるようになってしまっているからであります。
どういうことかと言いますと、そもそも風とは空気が温められたり冷やされたりして、周りの空気より軽くなったり重くなったりすることで、その空気が移動することによって生じる自然現象です。
つまり、窓際やドアぎわの「冷えた」ところの空気が、重くなり下へ下へと履い寄るように迫ってきて、コタツや暖房器で温められた空気は軽くなり上に上っていき、周りの冷えた空気を押し下げて、そして結果として空気の流れができてしまい、結果、体感としてもスースーするというわけです。
そして、残念ながら、今筆者もコタツに寝そべって床に直接PCを置いてこれを書いておりますが、そんな床にへばりついた者に対して、窓際やドアぎわからの冷気は容赦無く這い寄ってきて、筆者の顔を撫で、手を悴(かじか)ませているわけでございます。
この「風」を、できるだけ防ぐにはどのようにしたらよろしいでしょうか。
風の原理から考えてみたいと思います。
そもそも、「冷やされた」空気が常に発生してしまう「ゾーン」として、部屋の入り口のドアぎわや、床まである窓のサッシといった金属部分の冷え冷え部分があるわけです。
こうしたもともと冷えやすいゾーンに、「動かない空気の滞留区画」を作ることが、部屋の防寒の第一歩となります。
コタツの熱量を上げても、ストーブの火力を大きくしても、それは逆効果です。
ますます、部屋の隅や端っことの温度差が増してしまい、空気の通り道が太くなり、要するにより派手にふんだんにスースーしてしまうだけになってしまうわけです。
これでは逆効果です。
水道光熱費もバカになりません。
そこで、空気の流れを遮断するために、断熱するために最も良い方法を取ることにします。
それは、窓やドアの下部分に、滞留した空気の層を作ることです。
よく衝撃防止材として使われている透明ビニールのぷちぷちを窓に貼る、といった防寒方法が紹介されていまして、これは非常に的を射た対策なのではありますが、貼るのが面倒ですし、そもそも引き戸の場合は貼れない、という制約がございます。
そこで、代わりに、要するに滞留した空気の層を作れば良いのでありますので、アイロン台を横に立てて置くだけでも十分に防寒性能を発揮するというわけです。
スースーするの風の通り道をかなり遮断し、ドアとアイロン台の間には、滞留した冷たい空気の層が滞留しており、これが強力な防寒性能を発揮するわけです。
雪でつくったかまくらの中はあたたかい、それと同じです。
そういうことで、部屋の中での「防寒」については、風の通り道になりやすい、冷えた窓やドアの入口のところに、何かを立てかけるなり屏風を置くなりして、「流れない」滞留した空気の層を作り出し、風の通り道を遮断することが肝要である、という記事でした。
部屋は暖かくなりましたので、次は財布の中身も暖かくレシート以外で膨らませていきたい筆者からの記事は以上です。
(2018年12月12日 水曜日)