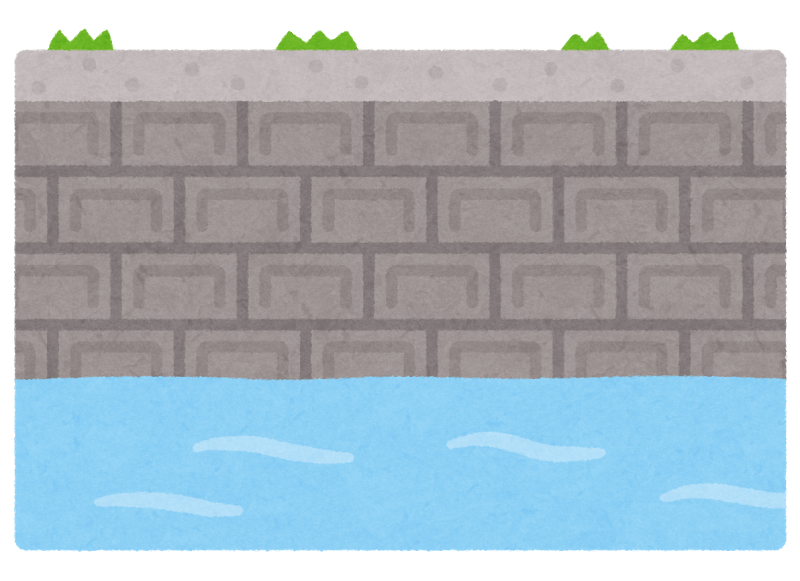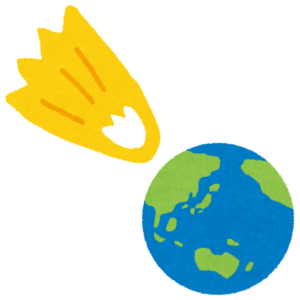(2018/01/05)2018年1月現在の代表的な仮想通貨の仕様の相違について比較しておきます
おはようございます。
2018年1月の記事です。
2018年は仮想通貨が世界中の一般消費者に浸透する年になると予想しておりますが、さて現時点における主要(メジャー)な仮想通貨のそれぞれの仕様の相違がありますので、主なものを挙げて理解の助けにしておきたいと思います(主に自分整理用です)。
現時点でおそらく時価総額が高いものを順に記載しますと
・ビットコイン(BTC)
・リップル(REP)
・イーサリアム(ETH)
・ライトコイン(LTC)
・ネム(XEM)
というところになると思います。
そして、原則としてこれら仮想通貨はいわゆるブロックチェーンという分散系監視システムによって運営されていますので、改竄や不正が入り込む余地は極限まで少なくなっております。
ただし、これらの通貨を運営していくためのインセンティブをどこに求めるかという点に少なくない違いを持っています。
仮想通貨運営上のインポータンスという概念がありまして、コンセンサスとして採用されているアルゴリズム(ルール)として、例えば
・ビットコインにおいてはPoW(プルーフ・オブ・ワーク)
というものがあります。
プルーフ・オブ・ワークとは仕事量(計算量)による承認、ととりあえず訳されます。
ビットコインの取引を承認してもらうために、承認を求めたい人や組織が、サーバーを立てて、大容量の電力を使ってコンピューターに計算をさせて、10分に一回といった電子取引ブロックを作っていくのです。
このハードワークの報酬として、その報酬を普通の通貨ではなくてビットコインそれ自体で受け取るため、そうした承認者のことを採掘者(マイナー)、承認作業のことを採掘(マイニング)と実際の金鉱堀りになぞらえて呼ぶというわけです。
しかしながら、このPoW(プルーフ・オブ・ワーク)という考え方では、コンピューターやサーバー自体に価値的上下はありませんので、単純に力技として大容量のCPUとサーバーを用意し、電力の安い国でブンブン連続で回し続ける者や、ビットコインそれ自体を含む大資本をもってスーパーコンピューターを多数所有して設備投資を続ける者が、その高速マイニングによってさらにビットコインを増やし獲得するという、どうしても資本主義の問題点である富の偏在貧富の格差がえらい勢いで進んでしまうという問題点があるのです。
この点、ネム(XEM)が採用しているインポータンス(運営アルゴリズム)は少し毛色が違っていて、ここがビットコイン他のメジャー仮想通貨とネム(XEM)が大きく違っているところになります。
XEMが採用しているのは、
・プルーフ・オブ・インポータンス(poI)といいます。
NEMのプルーフ・オブ・インポータンスは「ユーザーの重要度」によって報酬が分配される仕組みになっています。
NEMのアルゴリズムでは、「コイン(XEM)の保有数」と「取引の頻度」ということが、「重要度」に大きな影響を及ぼします。
ですので、ただコインをため込んでたくさん持っているだけでは報酬は得られず、それを取引していないと重要度は高まらないわけです。
同一アカウントで取引をしても重要度に影響を与えないため、他者と取引をすることになり、自然と富の分配が行われるというわけです。
勿論、この独自の指標は、「保有数」と「取引頻度」だけではなく、複数の複雑なアルゴリズムで設計されていて、そうしたコンピュータープログラム上の創造主の差配に従って適切に運営される分には等しくこの通貨の便益は世界中の隅々に行きわたるはずだということです。
そして、この報酬の原資は、XEMを使うときにこっそりと少しずつ上納される「取り扱い手数料」に求められます。
つまり、XEMという通貨は使うときに一部手数料がかかるのですが、その手数料を、他のXEM利用者に平等なNEMネットワーク重要度アルゴリズムによって振り分けているということです。
ですので、金鉱やビットコインのように、既存の全体通貨発行量を少しずつ増やしながら価格を安定させていくというような仕組みではなく、XEMは最初からすでに上限の約90億コインまで発行が終わってしまっています。
つまり、これ以上XEMが増えることはなく、そのコインの取引を行うたびに別枠で手数料を徴収し、それをファンドにしたもので、XEMの世界で重要なユーザーに報酬という形で振り分けるということなのです。
究極のエコシステムにも似て面白いと思います。
しかしながら、当然問題もありまして、XEM保有者が、手数料何か払う気なくてまったくXEMを利用しない、つまり取引承認を行わない事態になると、XEMネットワークは原資となる手数料を取ることができず、分配もされない、単なる電子クズとなり元の木阿弥になるというわけです。
なかなか、難しいものです。
雑駁ですが素人解説は以上です。
(2018年1月5日 金曜日)